睡眠時無呼吸症候群(SAS)にはどうやって気づく?症状を把握して早期発見しよう!

睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症すると、脳に十分な酸素を届けにくくなる影響で、生活習慣病や脳卒中など合併症のリスクが高まってしまいます。しかし、自分が睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症しているのか自覚するのは簡単なことではありません。
この記事では、すぐに睡眠時無呼吸症候群(SAS)の発症に気づき、早期発見および対策をスタートできるように、症状のチェック方法について解説します。
目次
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の放置はNG!早期発見が欠かせない理由とは?

眠っているときに短時間だけ呼吸が止まってしまう、何度もむせて目が覚めてしまうなど、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いをおもちの方は、その症状を放置しないように気を付けてください。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)を放置すると、生活における健康や人間関係に悪い影響が及ぶほか、死亡リスクが伴う合併症などを発症しやすくなります。
よって、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いがある場合は、放置するのではなく、睡眠専門のクリニックで早期発見をし、早めの対策に臨むことが重要です。まずは、放置せずに早期発見を目指すべき理由について紹介します。
参考:
睡眠時無呼吸症候群 / SAS | e-ヘルスネット(厚生労働省)
【睡眠時無呼吸症候群(SAS)を早期発見すべき理由1】日常生活に影響がある
睡眠時無呼吸症候群(SAS)を早期発見せずに放置すると、次のような問題が起き、日常生活に影響が出るかもしれません。
- 高血圧症のリスク
- 糖尿病のリスク
- 高尿酸血症のリスク
- 脂質異常症のリスク
例えば、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症すると、睡眠中に十分な酸素を取り入れられなくなってしまいます。結果として、血中酸素飽和濃度(血の中にある酸素の量)が減り、代謝量の減少や交感神経の活性化や酸化ストレスにより生活習慣病を発症しやすい身体へと変わりやすくなるのが特徴です。
また、睡眠時無呼吸症候群は睡眠時に交感神経が活性化するので、自律神経系が乱れる影響でストレスが溜まり、次のような問題に発展する恐れがあります。
- 家族とケンカをする頻度が増える
- イライラのせいで仕事や家事が手につかなくなる
- 些細なことで不機嫌になり空気を悪くしてしまう
- 些細なきっかけで傷害事件に発展した
また、ストレスを溜め続けた影響で、うつ病を発症するケースも少なくありません。仕事はもちろん家族との関係にも影響が及びやすい病気ですので、睡眠時無呼吸症候群(SAS)かもしれないと感じたら、ぜひ早期発見を目指してみてください。
【睡眠時無呼吸症候群(SAS)を早期発見すべき理由2】合併症のリスクが高まる
睡眠時無呼吸症候群(SAS)を早期発見せずに放置すると、生活習慣病だけではなく命に関わる合併症のリスクが高まります。参考として以下に、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因で併発しやすい病気をまとめました。
- 心不全
- 不整脈
- 脳血管障害
- 心筋梗塞
- 狭心症
まず睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症すると、血液に含まれる酸素の量が減り、脳に十分な酸素を届けられなくなることに注意しなければなりません。特に、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状が重い人ほど発症のリスクがあり、最悪のケースでは死亡するリスクもあるため、健康の為にも早期発見を目指しましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)で起きる主な症状とポイント

睡眠時無呼吸症候群(SAS)を早期発見するために覚えておきたいのが、病気の症状です。以下に、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症したことによって起こる主な症状を整理しました。
- 普段からよくいびきをかいている
- 睡眠中に何度も呼吸が止まる
- 睡眠中に息が乱れる
- むせて咳をする
- 寝汗をかきやすくなる
- 朝起きると口のなかが乾燥している
- 寝起きに頭痛がある
- 日中に身体がふらつく
- 物事に集中できない
- だるさや倦怠感が続く
あくまで一例ですが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)により、上記のような症状が起きやすくなります。もし経験がある、普段からよく感じているという方は、睡眠専門のクリニックを予約して診察を受けてみてください。
また、詳しく睡眠時無呼吸症候群(SAS)によって起こる症状を知りたい方は以下の記事がおすすめです。
どうやって気づく?睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状を早期発見する方法

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に起きるトラブルであることから自覚症状がない人も多くいます。
参考として、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状を早期発見する方法をまとめました。「もしかすると睡眠時無呼吸症候群(SAS)かもしれない」とお悩みの方は、ぜひチェックしてみてください。
【早期発見の方法1】セルフチェックをしてみる
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、次のセルフチェック項目を確認することで、症状が起きやすい身体なのか否かを判断できます。
- 眠りが浅いと感じている(眠気が残っている)
- 昼間に急な眠気を感じる
- 作業に集中できず注意力が下がっている
- 寝起きに口のなかが乾いてねばついている
- 疲れが取れないことに悩んでいる
- 鼻づまりが起きやすい
- 周囲の人よりも肥満体型気味である
セルフチェックの情報はあくまで目安ですが、あてはまる項目が多い人ほど睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症する可能性が高くなります。早期発見のためにもぜひチェックしてみてください。
また、セルフチェックについてより詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめです。
【早期発見の方法2】睡眠アプリを使用してみる
ひとり暮らしの方や、普段ひとりで眠っている人など、睡眠中の状況を指摘してもらいにくい人は、スマートフォンに睡眠アプリを導入して、睡眠中の状況を記録するのがおすすめです。例えば、睡眠アプリでは、次のような情報を記録できます。
- いびきの録音
- 呼吸の安定性
- 寝返りの回数
- 入眠時間と起床時間
寝る前にアプリを起動することで、睡眠中の状況を継続的に記録できるのが魅力です。睡眠時無呼吸症候群(SAS)の早期発見はもちろん自身の睡眠のリズムを知るきっかけにもなるため、興味がある方はぜひ導入してみてください。
【早期発見の方法3】市販の検査キットを利用してみる
近年では、一部のメーカーやECサイトで、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の簡易検査キットが販売されています。指先に装着した状態で眠ることで、脈拍数や体動、血中酸素飽和濃度を測定できるという便利な製品であり、そのほとんどが5,000~15,000円程度での購入が可能です。
ただし、検査キットは簡易的な情報を調べられる機器であることに注意してください。経験豊富な専門医から診察してもらい原因究明や治療法の提案まで受けたい方は、後述する睡眠専門のクリニックで診察をして、早期発見を目指すのがおすすめです。
【早期発見の方法4】睡眠専門のクリニックで診察を受ける
今すぐ睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症しているか否かをチェックしたい、何が問題なのかを詳しく知りたいという方は、睡眠専門のクリニックで診察を受けるのがおすすめです。睡眠やいびきの知識を豊富にもつ医師から、適切なアドバイスをもらえます。
また、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療法もあわせて提案してもらえるのがクリニックの魅力です。生活習慣のアドバイスはもちろん、対症療法、根本治療などを提案してもらえるので、早期発見のために時間を見つけてクリニックを予約してみてはいかがでしょうか。
クリニック探しについては下記の記事を参考にしてみてください。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)を早期発見したいならクリニックでの受診がおすすめ

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は複数の方法で早期発見が可能ですが、その中でも、効率的かつ正確なのがクリニックでの受診です。参考として、睡眠専門のクリニックで受けられる診察内容を詳しく解説します。
【クリニックでの診察内容1】専門医からの問診
まずクリニックを訪問したとき、最初に受けられるのが専門医からの問診です。日常的な睡眠の状況を確認し、睡眠に対してどのような悩みを抱えているのかをヒアリングしてもらえるので、思っていること、悩んでいることを医師に話してみてください。
また、問診の際に睡眠の悩みやトラブルの状況を共有しておくことで、必要な治療を提案してもらいやすくなります。窓口で現在の状況などを書き込む書類等をもらえるため、詳しく書き込んでおくとよいでしょう。
【クリニックでの診察内容2】簡易検査(アプノモニター)・精密検査(ポリソムノグラフィー)
問診を受けたのち、CPAP(シーパップ)療法といった対症療法を実施するために検査が必要だと診断された場合には、アプノモニターという装置を使った「簡易検査」、ポリソムノグラフィーという「精密検査」を受ける場合があります。
まず簡易検査では、次のような睡眠中の状態を検査します。
- 無呼吸やいびきの回数
- 血中酸素濃度
次に詳細検査では、より詳しい次のような情報を検査するのが特徴です。
- 脳波
- 眼球運動
- 筋電図
- 心電図
- いびきの回数
- 無呼吸および低呼吸の有無とその度合い
- 睡眠時の体の向きや下肢の動き
- 不整脈
- 脈拍の変動
- 血中酸素濃度の変化
なお、睡眠専門のクリニックなどで実施されている検査は、保険適用となるCPAP(シーパップ)療法といった対症療法を受ける場合に必要になります。もちろん、検査を受けることでわかる睡眠トラブルもありますが、気軽に早期発見を目指すのであれば、費用と時間のかかる検査ではなく、医師の診察で十分判断できますので、早めの受診をおすすめします。
また、詳しく検査の方法を知りたい方は、以下の記事がおすすめです。
参考:
睡眠時無呼吸症候群の検査―健康な眠りを取り戻すために―|林 千江里(順天堂医学)
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状かもしれないと思ったら、いびきメディカルクリニックにご相談ください

自身の睡眠の状況をセルフチェックしてみて、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症しているかもしれないと感じた人は、睡眠時の病気を早期発見するためにクリニックを受診するのがおすすめです。しかし、全国に複数あるクリニックのなかから、どのような病院を利用すべきかお悩みの人も多いでしょう。
「対症療法ではなく根本治療を受けたい」
「面倒な検査を受けずに治療をスタートしたい」
と考えている方は、すぐに治療を始められる根本治療「いびきレーザー治療」がおすすめです。
いびきメディカルクリニックでは、切らない いびきレーザー治療「パルスサーミア」を提供しているほか、詳細な検査をしなくても経験豊富な医師による診察で睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの睡眠トラブルを発見できます。生活習慣のアドバイスや相談者にあった治療法の提案から、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の早期発見・治療までをトータルサポートしているため、まずは無料カウンセリングをご利用ください。
よくある質問
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は次の方法で、早期発見につなげやすくなります。
- セルフチェックリストの活用
- 睡眠アプリの導入
- 簡易検査キットの利用
また、正確に睡眠時無呼吸症候群(SAS)を早期発見したいという方は、睡眠専門のクリニックを受診するのが確実です。医師に診察をしてもらうことにより治療方法の提案を受けられるので、無料カウンセリングを予約してみてください。





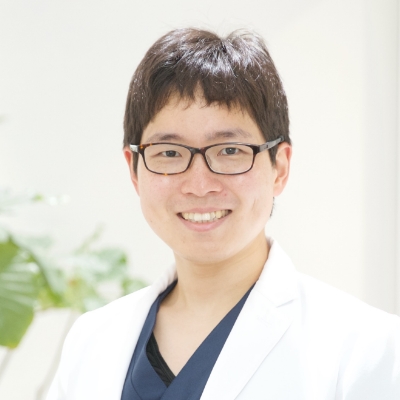




の検査と治療について/治療の費用相場・検査の流れ-150x150.webp)