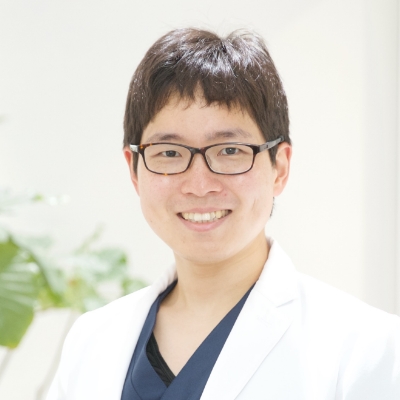【低酸素状態とは?】睡眠時無呼吸症候群の脳への影響について

【2023年8月23日更新】
「いびき」と聞くと、「ぐっすり眠っている」や「熟睡している」という印象を受ける人が多いですよね。おそらく、映画やアニメの中でぐっすり眠っている際に大きないびきをかいているシーンが描かれるからでしょう。
ですが、実際のいびきには、そんなポジティブな印象とは程遠い危険が潜んでいます。
そもそもいびきとは、呼吸が妨げられた際に発生する異常音のことで、うまく呼吸ができていない危険なサインです。
いびきを無視し続けることによって、睡眠時無呼吸症候群を発症し、最悪の場合脳へ大きなダメージを与えることになります。
この記事では、睡眠時無呼吸症候群と脳の関係について適切な理解を持てるように、危険性や症状の前兆まで詳しく解説していきます。
目次
睡眠時無呼吸症候群とは?

はじめに、睡眠時無呼吸症候群とはどのような病気なのか確認しておきましょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)とは、何らかの原因で睡眠中に気道が狭くなって、無呼吸状態に陥ってしまう病気です。
現在、睡眠時無呼吸症候群の罹患者は増加傾向にあり、2019年の報告では日本には940万人以上の患者がいると推計されています。しかも、中には検査や治療を受けていない人もいるため、実際の患者数はもっと多いという状況です。
そして、睡眠時無呼吸症候群には「閉塞性睡眠時無呼吸症候群」と「中枢性睡眠時無呼吸症候群」の2種類があります。
閉塞性睡眠時無呼吸症候群
閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA:Obstructive Sleep Apnea syndrome)は、肥満などの生活習慣やあごの骨格などが影響し、睡眠中に気道を塞がれてしまうことによって発生します。
無呼吸症候群に罹患している人のほとんどがこのタイプで、国内の推定患者数は900万人以上いるといわれています。
そして、閉塞性無呼吸の最大の特徴が寝ている間に発生するいびきです。発症すると毎晩のように大きないびきをかくようになります。
ですが、本人にはその自覚はない場合が多いため、家族や周囲の人に指摘されて初めて発症に気づくケースがほとんどです。詳しくは後ほど解説しますが、突然死につながりかねない合併症を発症する危険もあるため、いびきを自覚した場合は、速やかに医療機関を受診することが大切です。
中枢性睡眠時無呼吸症候群
もうひとつのタイプが、中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSA:Central Sleep Apnea syndrome)です。
中枢性は閉塞性とは異なり、呼吸の指示を出す大元の脳に異常をきたすことで、無呼吸状態を発症します。
脳の働きが低下する原因にはさまざまなものがありますが、特に多いのが心不全によるものです。心不全によって心臓の働きが低下し、血液をうまく全身に送り出せなくなることで、脳の呼吸中枢がうまく反応できなくなるのがひとつのプロセスと考えられています。
そして、閉塞性タイプとの大きな違いは、いびきをかかないことです。中枢性の場合は気道の閉塞が起こらないため、いびきの発生がありません。その代わり、閉塞性には見られない「チェーンストークス呼吸」という特有の呼吸が見られます。
閉塞性と同様、中枢性も放置すると命に関わる危険な疾患につながる可能性があるので、発見したら速やかに医療機関の相談し、治療を受ける必要があります。
睡眠時無呼吸症候群がもたらす脳の低酸素状態の危険性について

では、なぜ睡眠時無呼吸症候群が命を脅かすことがあるのでしょうか?それには、睡眠時無呼吸症候群がもたらす低酸素状態がさまざまな影響をもたらすことが原因です。
低酸素状態って何?
低酸素状態とは、血中の酸素濃度が低下している状態で、主に呼吸器や循環器疾患が原因で発症することが多いです。
今回の睡眠時無呼吸症候群の場合は、さまざまな原因で気道が狭くなり、無呼吸状態に陥ることで繰り返し低酸素状態になり、体にあらゆる悪影響をもたらします。
いわば睡眠時無呼吸症候群は、「夜間に起こる低酸素状態」といっても良いでしょう。
【注意】低酸素状態と低酸素血症・低酸素脳症は別物
ここでひとつ注意点があります。
「低酸素状態」と名前が似ている「低酸素血症」と「低酸素脳症」ですが、これらは「低酸素状態」とは全くの別物です。
確かに、3つとも血中の酸素濃度の低下を指す言葉ですが、「低酸素状態」は血中の酸素濃度が低下していること、あくまでその状態を指します。ですので、「低酸素状態」という病気があるわけではありません。
対して、「低酸素血症」は動脈血中の酸素が不足していることが原因で起こる症状で、血液中の酸素濃度を表すPaO2やSaO2の低下で定義することができます。
そして、「低酸素脳症」は「低酸素血症」によって脳への酸素供給が十分に行われず、重篤な脳の障害を起こしている状態を指します。主な症状は、意識障害や錐体外路徴候(手足がふるえたり、体がこわばったりする)、認知症、小脳失調、ミオクローヌス、コルサコフ症候群、痙攣などです。
まとめると、「低酸素状態」はあくまで血液中の酸素が低下している状態を指しており、それに該当するいくつもの疾患を広く定義しているイメージで、「低酸素血症」や「低酸素脳症」は血液中の酸素が低下していることによって体に引き起こされる症状を指す言葉です。
3種類とも非常に似ている言葉ですが、混同しないようにしましょう。
低酸素状態が続くと脳へどんなダメージがある?

それでは、睡眠時無呼吸症候群によって引き起こされた低酸素状態が、脳にどのような影響を与えるのか詳しく見ていきましょう。
睡眠時無呼吸症候群は脳卒中の原因になる
まずあげられるのが、脳卒中の誘発です。
脳卒中とは、脳の血管が詰まったり破れたりすることによって脳が障害を受ける病気で、脳の血管が詰まる「脳梗塞」と、破れる「脳出血」や「くも膜下出血」があります。
なぜ睡眠時無呼吸症候群が脳卒中につながるのか、それは高血圧を発症させるからです。
睡眠時無呼吸症候群によって繰り返し体が低酸素状態に陥ると、脳が酸素不足を感知して血流を活発にし、それを解消しようとします。
この血圧が高いまま維持され、定着した状態が「高血圧」です。
高血圧は進行すると次第に血管が脆くさせ、脳の血管にダメージを与えることで脳卒中につながります。
厚生労働省が発表した「令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、脳血管疾患の死因順位は第4位(6.8%)で、多くの人が脳卒中で命を落としているのがわかります。しかも、脳卒中は死亡率が高いだけでなく後遺症として麻痺や言語障害、寝たきりに発展する可能性が高いため、その後の生活の質を著しく下げる危険性もあります。
「寝ている間に無呼吸になるだけ」と甘く考えていると、思わぬところに落とし穴があるのが、この睡眠時無呼吸症候群の怖いところでもあるのです。
下記の記事でも、睡眠時無呼吸症候群と脳梗塞に関する解説をしているので、ぜひ参考にしてください。
記憶力の低下
仮に、脳卒中のような重篤な疾患に至らなくても、脳の低酸素状態の影響は甚大です。中でも、特に懸念されている脳に酸素が足りないことによる症状が、記憶力の低下です。
現在の睡眠研究において、人間の記憶の整理・定着には睡眠が大きな役割を果たしていることがわかっています。
ですが、睡眠時無呼吸症候群になると、無呼吸による低酸素状態によって慢性的な睡眠不足に陥るため、記憶力の低下が引き起こされるリスクが懸念されています。
しかも、無呼吸が将来の認知症の要因になる可能性も指摘されており、ますます睡眠時無呼吸症候群の早期発見・治療の必要性が呼びかけられています。
脳の認知機能低下は、生活のQOLに大きく関わる要素です。老後も健康的に生きるためには、少しでも異変を感じたら、なるべく早いうちに治療を受けることが大切です。
【他にもある】無呼吸による低酸素状態がもたらすリスク

脳だけでなく、睡眠時無呼吸症候群によってもたらされる低酸素状態は、さまざまなリスクを引き起こします。
生活習慣病
睡眠時無呼吸症候群になると、肥満や糖尿病などの生活習慣病になる可能性が高まります。
睡眠時無呼吸症候群によって肥満になる原因は、前章でも解説した高血圧が大きな原因です。また、最近の研究では、慢性的な寝不足は食欲をコントロールするホルモンの働きを低下させ、暴飲暴食を引き起こすともいわれています。
そして、糖尿病に関しては、睡眠時無呼吸症候群との医学的な因果関係はまだ不明点が多いです。ですが、無呼吸がもたらす低酸素状態と正常な酸素状態が何度も繰り返されることや、無呼吸から呼吸を再開する際の中途覚醒が、糖代謝異常に何らかの影響を及ぼすことによって、糖尿病が引き起こされると考えられています。
今後、さらなる研究が進められることが期待されます。
注意力欠如による交通事故
上記のような身体的に直接影響を与える合併症も重要ですが、睡眠時無呼吸症候群で無視できないのが注意力欠如による交通事故です。
睡眠時無呼吸症候群は、寝ている間に中途覚醒を繰り返すことで慢性的な睡眠不足に陥ります。ですが、本人には「最近寝不足気味だな…」程度の自覚しかありません。
そのような状態で車の運転を行ってしまうため、交通事故などの原因となってしまうのです。
実際、過去にも車、バス、トラック、電車などの運転手が無呼吸を発症しているにもかかわらず運転をしたことで事故を起こし、死傷者が出た事例が多数報告されています。
このように、個人の健康を脅かすだけでなく、多くの人の命や社会生活にも影響を与える睡眠時無呼吸症候群は、絶対に軽視してはいけない重大な病気であるといえるでしょう。
参考:
睡眠不足が引き起こす記憶障害
無呼吸症候群をそのままにしておくと
睡眠時無呼吸症候群の合併症
「もしかして睡眠時無呼吸症候群かも…」と思ったら

ここまでの内容を読んで、「私、もしかして睡眠時無呼吸症候群かも…」と思ったら、すぐに医療機関に相談し治療を受けることが先決です。
睡眠時無呼吸症候群の前兆かもしれない症状
特に、次のような症状に当てはまる人は、睡眠時無呼吸症候群を発症している可能性が高いといえるでしょう。
<睡眠中>
・睡眠中はほぼ毎回いびきをかく
・家族に指摘されるほどいびきの音が大きい
・睡眠中にしばしば呼吸が止まる
・息苦しさを感じて起きることがある
・寝ている間によくむせる
・尿意で何度も目が覚める
・寝汗をかく
・寝相が悪い
<起床時・日中の活動中>
・起きると喉が乾いている
・熟睡感がない
・睡眠時間は確保しているのに寝た気がしない
・倦怠感がある
・起床時に頭痛がある
・日中に強い眠気を感じる
・居眠りをしてしまう
・集中力が続かない
上記の中で、「朝起きたときいつも頭が痛い」「しっかり寝たはずなのに、脳に酸素が足りない感じがする」という人は、より脳の酸素不足が顕著に現れている可能性があります。次の記事では、寝起きに発生する頭痛について解説しているので、心当たりのある人はこちらも参考にしてください。
睡眠時無呼吸症候群の治療法
睡眠時無呼吸症候群の一般的な治療法として、多くの医療機関ではCPAP(シーパップ)治療が行われています。
「CPAP(シーパップ):経鼻的持続陽圧呼吸療法」は、鼻に装着したマスクから空気が送り込まれ、睡眠中の気道を開存させて呼吸をサポートする治療法です。現在、日本では睡眠時無呼吸症候群治療の第一選択肢とされています。
また、CPAP治療が適用されるのは閉塞性タイプの患者で、中枢性タイプの人は脳の機能低下を引き起こした原因(多くの場合は心不全)を解消する薬物療法や、生活習慣の改善を主軸に治療を行う場合が多いです。
いびきメディカルクリニックでは
睡眠時無呼吸症候群治療で最もポピュラーなCPAP(シーパップ)治療ですが、マスクから空気が送り込まれるのに慣れる必要があったり、睡眠時は毎回マスクをつける必要があったりなど、不便な点も多いのが実情です。
そこで、私たちいびきメディカルクリニックでは、最新のレーザー手術によっていびき・無呼吸の根本治療を行っています。
「パルスサーミア」というレーザー治療方法で、睡眠時の気道の閉塞を引き起こす喉粘膜をレーザーで引き締めることで、無呼吸を根本から解消します。
喉にレーザーを当てると聞くと、恐怖心を覚えるかもしれませんが安心してください。パルスサーミアで使用するレーザーは特殊仕様で、照射しても出血はなく痛みもほとんどありません。
しかも、術後わずかに現れる腫れや違和感も数日間で解消されるので、スムーズに日常生活に戻ることができます。それに施術時間もたったの15分程度なので、日帰り手術が可能です。忙しいサラリーマンや主婦の方にも、ぜひ受けていただきたい治療法です。
当院で治療を受けてみたいと思った方は、ぜひ無料カウンセリングにお越しください。専門のスタッフが、お客様の疑問や不安にとことんお答えいたします。
本記事の最後に設置している予約フォームからお問合せができるので、ぜひご活用ください。
まとめ

今回は、睡眠時無呼吸症候群と、脳の低酸素状態が引き起こすリスクについて解説しました。
睡眠時無呼吸症候群は、寝ている間に無呼吸状態に陥ることで慢性的な睡眠不足になる疾患ですが、放置すると低酸素状態をもたらし、脳卒中などのダメージを脳に与えます。
しかも、脳だけでなくその影響は全身に及ぶ可能性もあります。
睡眠時無呼吸症候群はれっきとした病気です。「寝ているときにいびきをかくだけ」と甘く見ずに、異変を感じたら速やかに医療機関に相談しましょう。
【よくある質問】
Q.睡眠時無呼吸症候群がもたらす低酸素状態とはなんですか?
A.睡眠時無呼吸症候群になると、気道の閉塞によって血中の酸素濃度が低下します。これが低酸素状態です。
Q.睡眠時無呼吸症候群で低酸素状態になると、どうして脳にダメージがあるのですか?
A.睡眠時無呼吸症候群によって低酸素状態になると、脳は酸素を取り込もうと血流を活発にし、その結果高血圧に陥ります。この高血圧が進行すると、いずれ脳の血管にもダメージを与え、脳卒中などの危険な脳の疾患につながる恐れがあるのです。