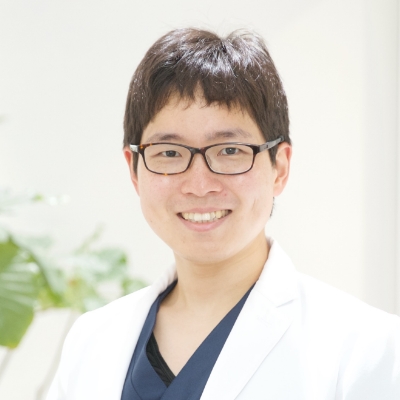ひどい寝汗で起きるのはなぜ?考えられる原因と快適な睡眠のための対策
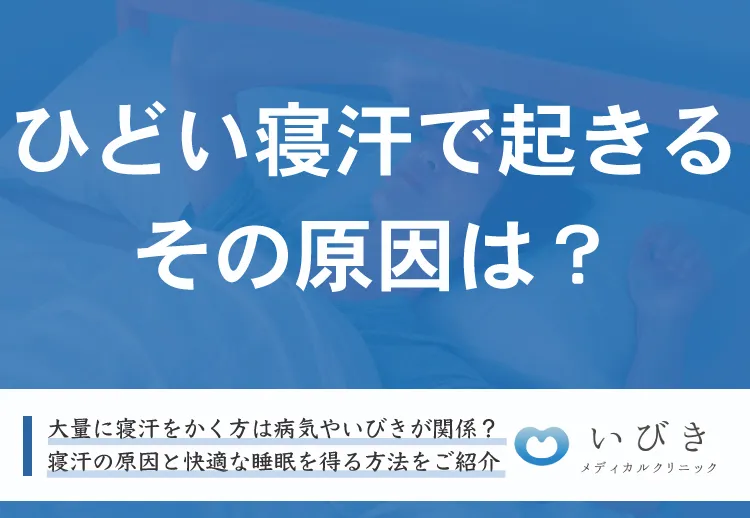
朝起きたら寝汗でびっしょり――そんな経験はありませんか?
寝汗は通常、体温調節のために起こる自然な現象ですが、毎晩のように大量の汗をかく場合、生活習慣や睡眠障害が関係していることも。特にいびきをかく人は、睡眠時無呼吸症候群などの影響が疑われます。
この記事では、寝汗の原因と対策、受診の目安や相談先についてわかりやすく解説します。
ひどい寝汗で起きる…その原因とは?

寝汗は、体温を調整するために生じる自然な現象です。特に暑い季節や厚着をして寝た場合には、発汗によって体の熱を逃し、体温を一定に保とうとします。そのため、ある程度の寝汗は正常であり、健康な体の働きの一つといえます。
しかし、
「汗でびっしょり濡れて目が覚める」
「毎晩のように大量の汗をかく」
というような状態が続く場合は注意が必要です。
ひどい寝汗の原因①:寝室の気温・湿度が高い
寝室の気温や湿度が高いと、寝汗が増えやすくなります。
夏場の暑さや暖房の効きすぎた部屋では、体が熱を逃がそうとして大量の汗をかきます。また、湿度が高いと汗が蒸発しにくく、体温調節がうまくいかず、さらに寝汗をかきやすくなります。
ひどい寝汗の原因②:ストレスや自律神経の乱れ
精神的なストレスや生活リズムの乱れは、自律神経のバランスに影響を与え、寝汗の原因になることがあります。
自律神経は、体温調節や発汗のコントロールを担う重要な役割を持っていますが、強いストレスを感じていると自律神経のコントロールがうまく機能しなくなります。それによって、睡眠中でも発汗が促進され、異常な寝汗をかくことがあります。
ひどい寝汗の原因③:アルコールの飲み過ぎ
アルコールを飲み過ぎると、アルコールの分解過程で発生する水分が汗として排出されるため、寝汗が増えやすくなります。
アルコールは肝臓で分解される際に、アセトアルデヒドという有害物質を経て、最終的に水と二酸化炭素になります。この過程で汗や尿として排出される水分量が増えるため、寝汗が多くなることがあります。
ひどい寝汗の原因④:【女性特有】妊娠
妊娠初期や後期には、基礎代謝を上昇させるホルモンの変動によって寝汗をかきやすくなります。
妊娠すると、体内でプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が増加し、基礎体温が上昇します。この影響で、妊婦は通常よりも体温が高くなり、発汗が増えやすくなるのです。特に妊娠初期や後期はホルモンの変動が大きく、自律神経も乱れやすいため、寝汗をかくことが増える傾向があります。
参考:
妊娠期について|JAPAN SPORT COUNCIL(日本スポーツ振興センター)
ひどい寝汗の原因⑤:疾患による影響
寝汗を引き起こす病気にはさまざまなものがあります。例えば睡眠中に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」や、発汗異常を引き起こす「甲状腺機能亢進症(バセドウ病)」などは、寝汗の症状が現れやすい疾患です。
また、ホルモンの変動が関係する更年期障害や、血糖値の急激な変動が影響する低血糖なども、発汗の原因になることがあります。
ひどい寝汗が続く場合、何らかの疾患が関係している可能性を疑いましょう。
ひどい寝汗をかく病気①:睡眠時無呼吸症候群(SAS)
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に何度も無呼吸状態に陥る病気です。代表的な症状の一つとして、寝汗をかくことが挙げられます。
その理由は、無呼吸状態では体が酸素不足を補おうとして頻繁に覚醒することで交感神経が活性化されるためです。この影響で発汗が増え、ひどい寝汗をかくことがあります。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の主な症状としては、寝汗のほかにいびきや日中の強い眠気、起床時の頭痛などが挙げられます。もし、これらの症状に心当たりがある場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を疑う必要があるでしょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について詳しく知りたい方は、下記記事も併せてご覧ください。
ひどい寝汗をかく病気②:呼吸器疾患(結核や肺炎など)
結核や肺炎などの呼吸器疾患は、体内で炎症が起こることで発熱や寝汗を引き起こすことがあります。特に結核では、夜間に異常な発汗が見られることが多いとされています。
呼吸器疾患の主な症状としては、寝汗のほかに長引く咳や痰、発熱、息苦しさなどが挙げられます。これらの症状が続く場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
ひどい寝汗をかく病気③:甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、代謝が異常に活発になる病気です。
甲状腺ホルモン(T3、T4)はエネルギー消費や体温調節に深く関わっており、その分泌量が増えると体温が上昇しやすくなり、発汗量が増えることがあります。
特にバセドウ病では、全身の代謝が活発化するため、手のひらや足の裏など特定の部位だけでなく、全身にわたって汗をかきやすくなるのが特徴です。
バセドウ病の主な症状としては、寝汗のほかに動悸や手の震え、体重減少、暑さを感じやすくなるなどが挙げられます。これらの症状が続く場合は、甲状腺機能の異常を疑い、早めに専門医に相談することが大切です。
参考:
甲状腺の病気|働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省)
ひどい寝汗をかく病気④:更年期障害【女性特有】
更年期障害では、暑くもないのに急に体がほてり、大量の汗をかくことがあります。
これは、ホルモンバランスの変化により自律神経が乱れ、体温調節がうまく機能しなくなるためです。特に、エストロゲンの分泌量が不安定になると、「ホットフラッシュ」と呼ばれる症状が現れ、寝汗が増えやすくなります。
さらに、更年期障害では動悸、不安感、イライラ、倦怠感などの症状も伴うことがあります。日常生活に支障が出る場合は、早めに専門医に相談することが大切です。
参考:
寝汗(発汗)の原因・症状と対策方法|更年期ラボ(大塚製薬)
男性も更年期障害を発症してひどい寝汗をかくことがある
男性も更年期障害によって寝汗をかくことがあります。
加齢やストレスの影響で男性ホルモン(テストステロン)の分泌が低下すると、自律神経が乱れ、体温調節がうまくいかなくなることがあります。その結果、寝汗やほてりなどの症状が現れることがあるのです。
ただし、男性と女性では更年期障害の症状がやや異なることもあります。 女性の更年期障害ではホットフラッシュをはじめとしたほてり、のぼせが起こりやすいのに対し、男性の場合は疲労感、性欲の低下、集中力の低下、イライラや不安感など、精神的な症状が目立つことが多いです。
これらの症状が続く場合は、男性更年期障害の可能性があるため、専門医に相談することが大切です。
参考:
男性更年期障害(加齢性腺機能低下症、LOH症候群)|一般社団法人 日本内分泌学会
ひどい寝汗をかく病気⑤:低血糖
低血糖になると、体が血糖値を上げようとして交感神経が活性化し、寝汗をかきやすくなります。
血糖値が正常範囲を下回ると、体はアドレナリンなどのホルモンを分泌して血糖値を維持しようとします。この影響で発汗が促進され、夜間に寝汗として現れることがあるのです。
こうした症状は「夜間低血糖」とも呼ばれ、糖尿病治療中の人だけでなく、健常な人でも食事の摂り方によっては発生することがあります。ひどい寝汗のほかに睡眠中の歯ぎしりやこわばり、悪夢などが頻繁に起きる人は「夜間低血糖」の可能性があるため、医師に相談するようにしてください。
参考:
歯ぎしり、寝汗…潜む意外な原因「夜間低血糖」|NIKKEI
ひどい寝汗をかく病気⑥:リンパ腫
リンパ腫では、免疫機能の異常や炎症反応により、寝汗をかきやすくなります。
リンパ腫は、リンパ球が異常に増殖する血液のがんの一種です。この病気では、体が異常な細胞を排除しようとする過程で発熱や炎症反応が起こり、それに伴い発汗が促進されることがあります。特に、寝汗はリンパ腫の特徴的な症状の一つです。
リンパ腫の主な症状には、寝汗のほかに発熱、体重減少、リンパ節の腫れ(首・脇の下・鼠径部など)があります。これらの症状が続く場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。
参考:
リンパ腫の原因・症状について|国立研究開発法人 国立がん研究センター
ひどい寝汗をかく病気⑦:多汗症
多汗症は、必要以上に汗をかいてしまう疾患です。その理由は、発汗をコントロールする自律神経の働きに異常が生じているためです。
多汗症の人は、寝ている間に大量の汗をかくことがあります。その原因としては、ストレスや緊張が代表的です。また、生活環境の変化や心理的な負担も異常な発汗を引き起こす要因とされています。
多汗症は、発汗量の異常な増加によって日常生活に支障をきたすこともあります。人よりも汗の量が多いと感じる場合は、多汗症の可能性を疑い、専門医に相談することが推奨されます。
ひどい寝汗で起きるのを防ぐための対策8選

ひどい寝汗が続くと、睡眠の質が低下し、疲労感や不快感が増すことがあります。寝汗の原因はさまざまですが、生活習慣や環境を見直すことで改善できる場合もあります。
本章では、寝汗を軽減するための具体的な対策を8つ紹介します。
寝汗の対策①:寝室の環境を整える
寝汗対策には、寝室の環境を整えるのが有効です。
特に、寝室の温度が高すぎると体が過剰に熱を持ち、発汗によって体温を下げようとするため、寝汗の量が増えてしまいます。また、湿度が高い環境では、汗が蒸発しにくく、体に熱がこもりやすくなります。
その結果、寝汗が多くなり、不快感が増す原因となります。
寝室の温度や湿度を適切に保つことで、寝汗を軽減し、快適な睡眠環境を整えることが可能です。
寝汗の対策②:寝具の改善
寝汗対策には、寝具の選び方も重要です。
特に、通気性が悪い布団やマットレスを使用していると、寝ている間に熱がこもりやすくなり、汗をかきやすくなります。さらに、吸湿性が低い寝具では、汗を十分に吸収できず、不快感が増す原因となります。
通気性や吸湿性に優れた寝具を選ぶことで、寝汗による不快感を軽減し、快適な睡眠をサポートすることができます。
寝汗の対策③:パジャマ・寝巻の改善
寝汗対策には、着用するパジャマや寝巻の素材を見直すことも有効です。
特に、吸湿性や通気性の低い素材のパジャマを着ていると、汗がこもりやすくなり、寝汗による不快感が増してしまいます。また、締め付けが強い衣類は、体温調節の妨げになることがあります。
吸湿性や通気性に優れた素材のパジャマを選ぶことで、寝汗の影響を抑え、快適な睡眠環境を作ることができます。
寝汗の対策④:ストレス管理をして寝る前はリラックスする
寝汗対策には、寝る前にリラックスし、ストレスを軽減することも重要です。
ストレスが溜まると、自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位に働くことで発汗が促進されることがあります。
寝る前にリラックスする時間を作ることで、自律神経が整い、寝汗の軽減につながる可能性があります。
寝汗の対策⑤:寝る前のアルコールを控える
寝汗対策には、寝る前のアルコール摂取を控えることを心がけることが大切です。
アルコールは体内で分解される過程で発汗を促し、夜間の寝汗の原因となることがあります。また、過度なアルコールは睡眠の質そのものを低下させることにもつながるため、できるだけ避けるのが効果的です。
寝る前のアルコール摂取を控えることで、寝汗の軽減や質の良い睡眠につながることが期待できます。
寝汗の対策⑥:寝る前にコップ一杯の水を飲む
ひどい寝汗の対策として、寝る前にコップ一杯の水を飲むことが有効です。
寝汗をかくと体は水分を失って脱水状態になり、体温調節がうまくいかずにかえって寝汗をかきやすくなることがあります。
この対策として、寝る前に適量の水を飲むことで睡眠中の水分不足を防ぎ、体温が安定して寝汗の軽減につながるとされています。ただし、就寝直前に大量の水を飲むと、夜間のトイレ回数が増えて睡眠の質が低下することもあるため、適量を意識することが大切です。
寝汗の対策⑦:適度な運動を取り入れる
寝汗対策には、適度な運動を習慣にすることも効果的です。
運動不足が続くと、自律神経のバランスが乱れやすくなり、体温調節機能にも影響を及ぼして寝汗をかきやすくなることがあります。また、運動によって汗をかく習慣がつくことは発汗のコントロールのしやすさにもつながるので、軽めの運動から取り入れると良いでしょう。
寝汗の対策⑧:規則正しい食生活
寝汗を軽減するためには、規則正しい食生活を心がけることも大切です。
特に、夜遅くの食事や脂っこい食べ物の摂取は、寝汗をかきやすくする要因のひとつです。
栄養バランスの取れた食事を意識し、食事の時間を一定にすることで、寝汗の軽減につながることが期待できます。
対策しても寝汗がひどいなら病院へ

寝室環境の見直しや生活習慣の改善をしても、ひどい寝汗が続く場合は、何らかの疾患が関係している可能性があります。
寝汗の原因には、睡眠時無呼吸症候群や甲状腺機能亢進症、リンパ腫などの病気が含まれることがあり、放置すると症状が悪化するおそれがあります。
病院を受診すべき目安と診療科について
ひどい寝汗が続き、かつ以下のような症状が見られる場合は、病院を受診することをおすすめします。
- 寝汗が大量である
- 毎晩のように寝汗をかく
- 寒いのに寝汗をかく
- 発熱や体重減少を伴う
- いびきを指摘されて、日中の眠気が強い
受診する診療科は内科が適しています。
内科では、睡眠時無呼吸症候群や甲状腺疾患など、寝汗の原因となる病気を幅広く診察してもらうことができます。また、必要に応じて、さらに専門的な検査や治療を受けることも有効です。もし、ひどい寝汗に加えて大きないびきが見られる場合は、睡眠時無呼吸症候群が疑われます。その場合は、いびき治療を専門に行うクリニックを受診するのがおすすめです。
いびきメディカルクリニックは、いびき治療を専門に行うクリニックで、これまでたくさんの患者様のいびきや睡眠時無呼吸症候群の治療を行ってきました。思い当たる症状がある方は、ぜひ一度相談してみてください。
よくある質問
連日のひどい寝汗に加えていびきが見られる場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性が高いです。