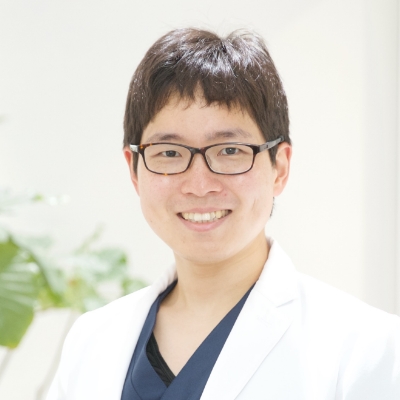【寝ても寝ても眠い女性へ】年代別の原因と改善方法を徹底解説!

「しっかり寝ているはずなのに、寝ても寝ても眠い」と感じる女性は少なくありません。生活習慣の乱れやストレス、ホルモンバランスの変化、年代が変わることによる生活スタイルの変化、さらには睡眠を妨げる疾患の影響など、さまざまな原因が考えられます。
本記事では、「寝ても寝ても眠い」女性を対象に、20代、30代、40代、そして50代以降の年代別に原因を詳しく解説し、具体的な対策や改善方法をご紹介します。
また、症状が長期間続く場合に病院を受診すべきタイミングについても解説していくので、「寝ても寝ても眠い」原因を知り、質の良い睡眠を取り戻して快適な毎日を目指しましょう。
目次
女性が寝ても寝ても眠いと感じる主な原因

女性が「寝ても寝ても眠い」と感じる原因は、多岐にわたります。生活習慣の乱れやストレス、女性ホルモンの影響、さらには睡眠の質を低下させる疾患が関係している場合もあります。本記事では、それぞれの原因を詳しく解説していきます。
女性の寝ても寝ても眠い原因①:生活習慣の乱れやストレス
生活習慣の乱れやストレスは、女性が「寝ても寝ても眠い」と感じる一般的な原因の一つです。
不規則な生活リズムや夜更かし、寝だめなどの乱れた睡眠習慣は、体内時計を狂わせ、睡眠のリズムに影響を与えます。さらに、運動不足や食生活の偏りなども睡眠の質を下げる要因です。
また、職場や家庭でのストレスが蓄積すると、自律神経が乱れ、十分にリラックスできないまま眠りについてしまうこともあります。これにより、深い眠りが得られず、翌日に疲労感や眠気を持ち越してしまいます。
日々の忙しさでつい後回しにしがちな生活習慣ですが、これを整えることが、快適な睡眠と日中の活力を取り戻す第一歩になります。
女性の寝ても寝ても眠い原因②:女性ホルモンの乱れ
女性ホルモンのバランスが崩れることで、「寝ても寝ても眠い」と感じる場合があります。
特に月経前症候群(PMS)や妊娠、出産、更年期障害などは、体調の変化を引き起こし、眠気や疲労感を増幅させる原因となります。それぞれの状況について詳しく解説します。
月経前症候群(PMS)
月経前症候群(PMS)は、生理が始まる前の3日から10日程度にわたり、身体的・精神的な不調を感じる症状の総称です。
詳細なメカニズムはまだ解明されていませんが、発症には女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロン)の急激な変動が関係していると考えられています。そして、PMSは睡眠に与える影響も大きいです。ホルモンバランスの乱れによる不安感や、体温の上昇、そして情緒不安定に伴って「寝ても寝ても眠い」と感じるとされています。
このように、PMS期間中は質の良い睡眠が取れないことで、日中の強い眠気や疲労感につながるのです。
妊娠・出産・育児
妊娠中の女性が「寝ても寝ても眠い」と感じるのは、体と心に起こる大きな変化が影響しています。
妊娠初期は、ホルモンバランスの急激な変化や妊娠への不安、ストレスが原因で眠りにくくなり、眠気を感じやすくなります。赤ちゃんの成長によって胎動が激しくなることで目が覚めたり、膀胱が圧迫されることで頻繁にトイレに行きたくなったりするのも原因です。
さらに、プロゲステロンが基礎体温を高く保つため、寝つきが悪くなったり、深い眠りが得られなかったりすることも考えられています。このような状態が続くと、日中の強い眠気につながり、「寝ても寝ても眠い」と感じやすくなります。
そして、妊娠期間を終えて出産し、育児をするようになっても、睡眠不足は続く場合が多いです。新生児の授乳やおむつ替えで夜間に何度も起きる必要もあり、まとまった睡眠時間を確保するのが難しくなりますので、睡眠時間を上手くコントロールしましょう。
更年期障害
更年期には、ホルモンバランスの変化が原因で「寝ても寝ても眠い」症状を訴えることが増えます。
女性は閉経すると、エストロゲンやプロゲステロンの分泌が減少することで、自律神経が乱れやすくなり、睡眠の質が低下することが知られています。特に、ほてりや発汗といった血管運動神経症状が夜間に起こると、途中で目が覚めたり、寝つきが悪くなったりする場合があります。
また、更年期には不安感や抑うつといった精神症状が現れることもあり、これが不眠の一因となることもあります。
参考:
PMSがある人は睡眠の質が低下している| PMSラボ(大塚製薬)
女性の寝ても寝ても眠い原因③:睡眠の質を低下させる疾患の影響
生活習慣や女性ホルモンの乱れに心当たりがないのに寝ても寝ても眠い場合、睡眠の質を低下させる疾患が関係している可能性があります。
例えば、過眠症やむずむず脚症候群、うつ病などは、深い眠りを妨げる要因となり得ます。また、睡眠時無呼吸症候群が原因で、睡眠中に何度も目が覚めてしまうこともあります。
このような疾患が関係している場合、単なる疲労ではなく根本的な原因を突き止めるために、専門医の診断を受けることが重要です。
【年代別】女性が寝ても寝ても眠いと感じる原因について解説

女性が「寝ても寝ても眠い」と感じる原因は、年代ごとに異なる生活環境や身体の変化によって変わることがあります。ここでは、20代から50代以降まで、それぞれの年代に特有の原因について詳しく解説します。
20代の場合(キャリアと自由を満喫する時期)
20代の女性が「寝ても寝ても眠い」と感じる原因には、不規則な生活習慣や過度なストレスが関係していることが多いです。
20代は新しい環境で仕事や生活をスタートさせる時期です。しかしその中で、仕事や学業のプレッシャー、夜更かしやSNSが睡眠の質を低下させる要因になることがあります。
また、プライベートも充実させようとするあまり、昼夜逆転の生活に陥るケースも見られます。若いからといって体に負担をかけすぎると、慢性的な疲労感につながりやすいため、生活リズムを整えることが大切です。
30代の場合(仕事と家庭の両立に挑戦する時期)
30代の女性は、仕事と家庭の両立に挑戦する中で、「寝ても寝ても眠い」と感じることがあります。
仕事の責任が増えたり、家事や育児に追われたりすることで、心身ともに疲れがたまりやすい時期です。特に子育て中の女性は、夜間の授乳や家事でまとまった睡眠が取れず、慢性的な睡眠不足に陥りやすいです。また、ストレスや疲労が蓄積すると、自律神経が乱れて入眠や熟睡が難しくなることもあります。無理をしすぎず、休息の時間を確保することが重要です。
40代の場合(仕事の責任が増える中で体の変化を感じ始める時期)
40代の女性は、仕事の責任が増す一方で、更年期による体調の変化が始まる時期でもあります。
ホルモンバランスの乱れにより、自律神経が影響を受け、「寝ても寝ても眠い」と感じやすくなります。また、仕事や家庭でのストレスが重なることで、心身が緊張状態に陥り、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりするケースも多いです。この年代では、自分の健康を意識し、生活習慣を見直すことが大切です。
50代以降の場合(加齢に伴って睡眠サイクルが変化する時期)
50代以降の女性は、加齢による体内リズムの変化が原因で、寝ても寝ても眠い状態になりやすくなります。
年齢を重ねると、若い頃と比べて睡眠時間そのものが減少するため、熟睡感が減少します。また、女性ホルモンの分泌量も少なくなるため、自律神経が乱れ、深い眠りを得にくくなります。さらに、夜間の頻尿や慢性的な痛みなど、加齢特有の身体的な問題も睡眠を妨げる要因です。
この時期は、規則正しい生活リズムを心がけるとともに、睡眠環境を整えることが重要です。
女性が寝ても寝ても眠いときに考えられる主な睡眠疾患

「寝ても寝ても眠い」状態が続く場合、睡眠を妨げる疾患が関係している可能性も考えられます。ここでは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)をはじめ、過眠症やむずむず脚症候群など、睡眠の質を低下させる主な疾患について解説します。
いびき・睡眠時無呼吸症候群(SAS)
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が一時的に停止し、睡眠中の大きないびきや日中の強い眠気、疲労感を引き起こす疾患です。
本疾患は極度の肥満に伴って発症するのが一般的ですが、女性は女性ホルモンのおかげで男性よりも発症が抑えられています。しかし、閉経すると女性ホルモンの分泌量が減るため、女性も同じように発症リスクが高まります。また、妊娠中は急激な体重増加によってSASが生じやすくなることも知られており、胎児の健康リスクにつながることもあるので注意が必要です。
さらに、日本人はもともと首が短くて太く、そして下あごが小さい人が多いです。そのため、大したことない肥満でも睡眠中に気道が狭くなっていびきをかき、SASを発症するケースも見られます。特に、女性は小顔で下あごが小さめの方が多いので、若くて痩せている女性でもSASの発症には注意しましょう。
睡眠時無呼吸症候群について詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
過眠症
過眠症は、十分な睡眠をとっても日中に強い眠気が続き、日常生活に支障をきたす疾患です。
過眠症の中でも代表的な疾患は「ナルコレプシー」と呼ばれ、日中の過度な眠気に加えて、情動脱力発作(突然の一時的な筋力低下の発作)、入眠時または覚醒時の幻覚、睡眠麻痺などの症状が見られます。しかし、現在のところナルコレプシーを発症する原因は不明とされています。
他にも、過眠症には「特発性過眠症」や「反復性過眠症(クライネ-レビン症候群)」といった疾患があり、共に十分な睡眠時間にもかかわらず、日中に「寝ても寝ても眠い」と感じます。
このような寝ても寝ても眠たい状態が続くと、仕事や家庭での生活に悪影響を及ぼします。もし自分では原因が特定できない場合や、眠気が長期間続く場合は、専門医に相談して適切な診断と治療を受けることが重要です。
むずむず脚症候群
むずむず脚症候群は、脚に不快感を覚えてじっとしていられなくなる症状で、特に夜間に発生することが多い疾患です。この症状は、睡眠の質を著しく低下させ、寝ても寝ても眠い状態を引き起こす原因になることがあります。
特に、月経がある女性では、出血に伴う鉄欠乏性貧血がむずむず脚症候群を誘発・悪化させることが知られています。また、妊娠後期(妊娠28週以降)も脚の不快感が生じやすい時期です。
このようなリスクを軽減するためには、日頃から鉄分を意識的に摂取することが重要です。食事を改善するだけでなく、サプリメントなども活用し、体内の鉄分を補いましょう。
うつ病
うつ病は「寝ても寝ても眠い」と感じる原因の一つであり、不眠と密接に関連する疾患です。
日本では、うつ病患者の84.7%に不眠症状がみられるとの報告があります。不眠はさまざまな形で現れ、総睡眠時間の減少や深い眠りの不足を引き起こします。また、不眠はうつ病の経過にも影響を与え、治療が長引いたり、再発リスクが高まったりする要因となることが知られています。
さらに、不眠そのものがうつ病を発症するリスクを2倍に高めるともいわれています。うつ病に不眠が併存する場合は、両方の治療を同時に進めることが重要です。特に、女性はさまざまな要因でホルモンのバランスが乱れがちで、そして仕事でもプライベートでも毎日活動的に過ごしています。その中で、うつ病や不眠症状を発症することもあるでしょう。
睡眠の問題を軽視せず、専門医に相談することが症状改善の鍵となります。
参考:
「その不眠、うつ病かも」相互関係について専門家が解説|エーザイ株式会社
起立性調節障害
起立性調節障害は、自律神経の乱れによって脳への血流が低下し、立ち上がった際にめまいや立ちくらみ、倦怠感などの症状が現れる疾患です。この症状は、午前中に強く出る傾向にあるため、夜眠れずに起床時間が遅くなるという状態に陥ります。
子供に多い症状ですが、大人の女性でも発症することがあり、ホルモンバランスの変化や日常的なストレスが「寝ても寝ても眠い」などの症状を悪化させる可能性があります。また、天候や気圧の変化、特に雨の日や台風の時期には体調が悪化することが知られています。これに加えて、水分不足や活動量の低下による血液循環の悪化も考えられます。
症状が軽いうちは生活改善で対処可能な場合もありますが、重症化すると日常生活に支障をきたすため、早期の発見と適切な治療が必要です。
女性が寝ても寝ても眠いと感じるときにおこなってほしい対策

女性が「寝ても寝ても眠い」状態を改善するためには、生活習慣の見直しや睡眠環境の整備、ストレス解消などの具体的な対策が重要です。この章では、すぐに実践できる方法を詳しく解説します。
生活習慣を改善する
「寝ても寝ても眠い」状態の改善には、生活習慣の見直しが欠かせません。就寝・起床時間を一定に保ち、食生活を整え、夜遅くの食事やカフェイン摂取を控えるなどの工夫が効果的です。
就寝・起床時間は毎日一定に
毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きる習慣をつけることは、体内時計を整えるために重要です。
不規則な生活リズムは、自律神経を乱し、眠気や疲労感を増幅させる原因になります。また、休日だからといって長時間寝すぎるのも逆効果です。週末に寝だめをすると、平日と休日で大きく異なる生活リズムを送ることになり、体がまるで時差ぼけのような状態になります。
そのため、平日・休日関係なく、毎日一定の時間に寝起きすることは非常に大切な習慣です。
朝食をしっかり摂って、カフェイン・アルコールは控えめに
朝食を摂ることで体内時計をリセットし、一日のリズムを整える効果があります。特に、栄養バランスがしっかり整った朝食は、脳と体の目覚めを促し、エネルギー補給に役立ちます。一方で、カフェインやアルコールの摂取には注意が必要です。
カフェインは覚醒作用があるため、夕方以降に摂取すると入眠を妨げる可能性があります。アルコールは一見眠りやすくなるように感じられますが、睡眠が浅くなり、夜中に目が覚める原因となることが知られています。
これらを意識することで、睡眠の質を向上させ、「寝ても寝ても眠い」状態の改善に繋がります。
深夜のドカ食いは避ける
夜遅くに大量の食事を摂ると、胃腸が活発に働くことで体が休息モードに入れず、睡眠の質が低下します。特に、脂っこい食べ物や消化に時間がかかる食品は、体への負担が大きく、翌日の疲労感や「寝ても寝ても眠い」状態を引き起こす原因になります。一方で、シフトワークなどで夜遅くに食事をとらざるを得ない場合もあるでしょう。
基本的には、夕食を2回に分けて食べる「分食」(おにぎりなどの主食を夕方に摂り、帰宅後の遅い時間におかずなどの副食を軽くとること)が推奨されていますが、「どうしても寝る前に小腹が空いて眠れない」という場合は、消化に良いものを少量とるのがおすすめです。
例えば、あっさりとしたスープやおかゆなどは体に優しく、胃腸への負担を軽減します。このような工夫をすることで、深夜の食事が睡眠に与える影響を最小限に抑えられます。
睡眠環境を整える
快適な睡眠を得るためには、寝室の環境を整えることが重要です。光や音、温度・湿度を適切に調整し、リラックスできる空間を作ることで、「寝ても寝ても眠い」状態の改善に繋がります。
寝室の光・音・温度・湿度を睡眠に適したものに
寝室環境を整えることは、良質な睡眠を得るために欠かせません。
寝室の光は、睡眠の質に大きな影響を与えます。就寝前には部屋の照明を落とし、夜間はできるだけ暗く保つことが推奨されています。寝室には遮光カーテンを使用するのがおすすめです。また、静かな環境を確保することも重要で、騒音は睡眠効率の低下や覚醒頻度の増加と関連しているとされています。
温度に関しては、夏はエアコンを使用して寝室を涼しく保ち、冬は十分な寝具を用いて暖かさを維持することが大切です。適切な温度環境を整えることで深部体温の変動が円滑になり、入眠しやすくなります。湿度も快適な範囲を保つことで、睡眠時の呼吸を助け、体のリラックスを促します。これらの工夫を取り入れることで、体内リズムが整い、「寝ても寝ても眠い」状態の改善が期待できます。
寝る直前までスマホを見るのは控える
寝る直前までスマホを使用することは、睡眠の質を大きく低下させる原因になります。
スマホの画面から発せられるブルーライトは、体内時計を司るメラトニンの分泌を抑制し、入眠を妨げます。また、SNSや動画をチェックすることで脳が刺激され、リラックスしづらくなることも影響の一つです。このため、就寝の1〜2時間前にはスマホの使用を控えることが推奨されています。どうしてもスマホを使う必要がある場合は、ブルーライトカットのフィルターを使用したり、画面の明るさを最低限に抑える設定を活用したりすると良いでしょう。
ストレスを解消する
ストレスを解消することで、心身の緊張を和らげ、質の良い睡眠を得ることができます。湯船に浸かるなどのリラックス法を取り入れ、「寝ても寝ても眠い」状態の改善を目指しましょう。
毎日しっかり湯船に浸かってリラックス
就寝前に湯船に浸かることは、睡眠の質を向上させるために非常に効果的です。
ヒトの深部体温は日中に上昇し、夜間に低下するリズムを持っていますが、入浴することで手足の血管が拡張し、熱放散が促進されて深部体温がスムーズに低下します。
この体温の変動は、入眠しやすい状態を作り出すきっかけの一つとされています。また、入浴には筋肉を緩め、心身をリラックスさせる効果もあります。毎日の入浴を習慣にし、質の良い睡眠を手に入れることで、「寝ても寝ても眠い」状態から解放される助けとなります。
眠れないときは一度ベッドから離れる
無理に眠ろうとすることは、かえって寝つきを悪化させる原因になります。
眠気が訪れていない状態でベッドに留まると、脳が興奮してしまい、寝つけないことへの不安や日中の悩みが頭を占めてしまいます。
この悪循環を防ぐため、なかなか寝つけないときは一旦ベッドを離れることが推奨されています。静かで暗めの安心できる場所でリラックスし、深呼吸などをして安静に過ごしましょう。眠気が訪れてからベッドに戻ることで、スムーズな入眠が期待できます。
以下では他の睡眠の質を高める方法をおまとめしています。睡眠にお悩みの女性はぜひ参考にしてみてください。
女性が寝ても寝ても眠いときに病院へ行くタイミングは?

「寝ても寝ても眠い」状態が長期間続く場合、疾患が隠れている可能性があります。この章では、いびきやPMS、更年期障害など、病院で診てもらうべき具体的な症状と受診の目安を解説します。
長期間眠気が取れないとき
「寝ても寝ても眠い」状態が長期間続き、日常生活に支障をきたす場合は、病院での診察を検討しましょう。
慢性的な眠気は、睡眠を妨げる疾患が関与している可能性があります。放置すると症状が悪化し、健康や生活の質に大きな影響を与えることも懸念されるため、早めに専門医を受診し、適切な治療を受けましょう。
いびきがあるとき
いびきが頻繁で音量が大きい場合や、睡眠中に呼吸が止まるような症状(無呼吸)がある場合は注意が必要です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、気道が狭くなることで呼吸が妨げられる疾患で、日中の強い眠気や集中力の低下、高血圧や心血管疾患のリスクを増大させることがあります。そして、頻繁ないびきはSASを発症していることを示す重要なサインです。
いびきや無呼吸が見られる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
いびきメディカルクリニックでは睡眠時無呼吸症候群の根本治療を目指せます
いびきメディカルクリニックでは、「パルスサーミア」という治療法を用いて、いびきや睡眠時無呼吸症候群(SAS)の根本的な改善を目指しています。
パルスサーミアは、レーザー技術を活用して気道を広げる治療で、体への負担が少ないのが特徴です。また、この治療は短時間で済むため、忙しい方でも取り入れやすく、治療後は睡眠の質が向上し、日中の眠気や疲労感の改善が期待できます。
いびきや無呼吸が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。
月経前症候群(PMS)や更年期障害で悩んでいるとき
月経前症候群(PMS)や更年期障害によって「寝ても寝ても眠い」と悩んでいる場合は、婦人科を受診しましょう。
月経前症候群(PMS)や更年期障害によるホルモンバランスの乱れは、睡眠の質を大きく低下させる原因となります。
これらの症状に心当たりがある場合は、速やかに婦人科を受診しましょう。適切な治療が受けられ、ホルモンバランスを整える手助けとなります。
過眠症などの睡眠障害が疑われるとき
過眠症などの睡眠障害によって「寝ても寝ても眠い」と感じる場合は、睡眠外来などの専門クリニックを受診しましょう。
過眠症やむずむず脚症候群などの睡眠障害は、脳の睡眠制御機能や体の神経系に異常がある場合があるため、専門的な知識を持った医師による治療が必要です。特に日中の眠気が強く、生活に支障をきたしている場合は、早期の治療が必要でしょう。
早めの受診が症状の改善につながり、日常生活を快適にする第一歩となります。
睡眠習慣を整えて「寝ても寝ても眠い」状態から解放されよう
「寝ても寝ても眠い」状態を改善するには、生活習慣や睡眠環境を見直し、ストレスを解消することが大切です。それでも症状が続く場合は、病院で適切な診断と治療を受けることを検討しましょう。
専門医の力を借りながら、良質な睡眠を取り戻し、日々の生活をより快適にしていきましょう。
関連する下記記事も併せてチェックしてみてください。
よくある質問
睡眠不足といびきの症状が見られる場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を発症している可能性があります。