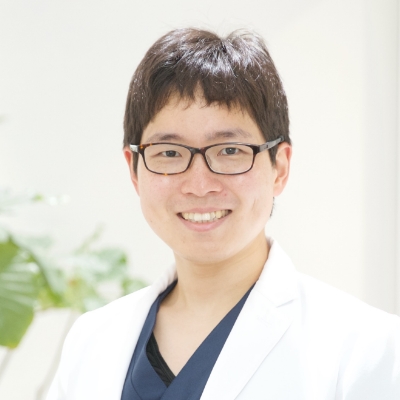細切れ睡眠とは?原因と改善策を知ってストレスなく快眠を目指そう!
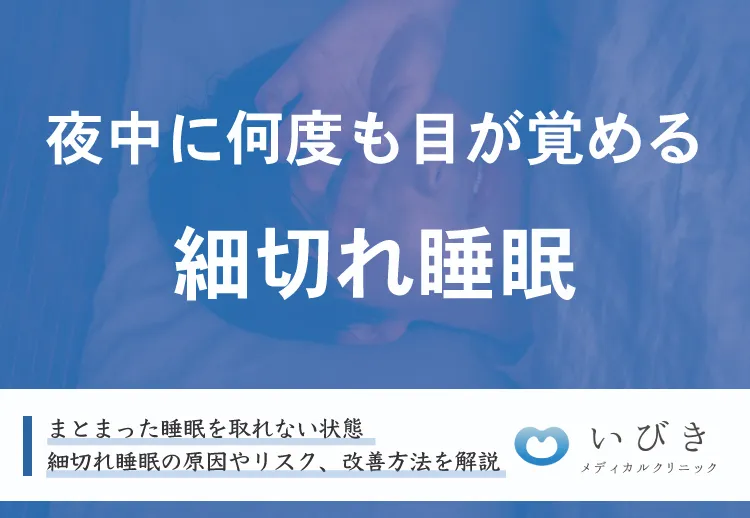
「夜中に何度も目が覚めてしまう」
「朝起きても疲れが取れない」
こんな細切れ睡眠に悩んでいませんか?
細切れ睡眠とは、一度にまとまった睡眠を取れず、眠りが断続的に中断される状態を指します。原因は加齢やストレス、不規則な生活習慣、さらには病気が隠れている場合もあります。このような状態が続くと、心身に大きな負担をかけるだけでなく、健康リスクを高めることにもつながります。
この記事では、細切れ睡眠の原因やリスクを解説するとともに、改善するための具体的な方法を紹介します。また、専門医による治療が必要なケースについても詳しく説明します。細切れ睡眠を改善して、質の良い眠りと健康を取り戻しましょう。
目次
細切れ睡眠とは?

細切れ睡眠とは、一度にまとまった時間の睡眠を取れず、眠りが断続的に中断される状態を指します。
本来、睡眠は深い眠り(ノンレム睡眠)と浅い眠り(レム睡眠)が一定のリズムで繰り返されることで、体と心が十分に休息を取れる仕組みになっています。そのため、多くの人は6〜8時間程度眠るのが通常です。
しかし、細切れ睡眠ではこのリズムが崩れ、睡眠が細かく分断されるため、質の高い睡眠を確保することが難しくなります。こうした睡眠の中断は自律神経やホルモンバランスに影響を与え、体を十分に休ませることができません。
細切れ睡眠に悩む方は、自身の睡眠の様子を振り返り、改善を行うことが大切です。
レム睡眠とノンレム睡眠については、下記記事をご覧ください。
細切れ睡眠の原因は?まとまった睡眠を取れない理由

細切れ睡眠の背景には、加齢によるホルモンバランスの変化やストレス、不規則な生活習慣、カフェインやアルコールの摂取、さらには睡眠を妨げる疾患などが挙げられます。この章では、それぞれの原因を詳しく解説し、まとまった睡眠を取れなくなる理由を紹介します。
加齢によるメラトニン分泌の減少
加齢に伴い、睡眠に深く関わるホルモン「メラトニン」の分泌量が減少することが知られています。メラトニンは、眠る時間が近づくと脳から分泌され、体をリラックスさせて自然な眠りへと導く役割を果たします。
しかし、このホルモンは年齢を重ねるごとに分泌量が減る傾向にあり、その結果、眠りが浅くなったり、夜中に何度も目が覚めてしまったりすることが増えます。
また、高齢になると日中の活動量が減ることで体が疲れにくくなり、夜に眠りづらくなることがあります。このような変化が重なることで、まとまった睡眠が取りにくくなります。
メラトニンと睡眠の関係について詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
ストレスによる自律神経の乱れ
ストレスは睡眠に大きく影響を与える要因のひとつです。
ストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、交感神経が優位な状態が続いてしまいます。本来、夜間は副交感神経が活発になり、体がリラックスすることで眠りにつく準備が整いますが、ストレス下ではこの切り替えがうまくできません。
その結果、寝つきが悪くなり、夜中に何度も目が覚める細切れ睡眠が起きやすくなります。
夜寝る前のカフェインやアルコール
夜間にカフェインやアルコールを摂取すると、睡眠の質が低下し、細切れ睡眠を引き起こす原因となります。
カフェインは、覚醒作用があることで知られています。コーヒーや紅茶だけでなく、エナジードリンクやコーラにも含まれており、摂取後長時間にわたって眠気を抑える効果が続くため、寝つきを悪くしたり、睡眠を浅くしたりする可能性があります。
一方、アルコールは一見リラックス効果があるように感じられますが、実際には体内で代謝される過程で睡眠が妨げられます。
これらの飲料を寝る前に摂取する習慣がある場合、知らず知らずのうちに細切れ睡眠を招いている可能性があるため、注意が必要です。
参考:
食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ&A ~カフェインの過剰摂取に注意しましょう~|厚生労働省
不規則な生活習慣
不規則な生活習慣は、細切れ睡眠を引き起こす大きな原因のひとつです。
例えば、毎日異なる時間に寝たり起きたりする生活を続けると、体内時計が乱れ、スムーズに睡眠に入れなくなることがあります。また、夜遅くまでスマートフォンやパソコンの画面を見ていると、ブルーライトの影響で脳が覚醒状態になり、眠りが浅くなることもあります。
さらに、夜食や深夜のドカ食いも、消化活動が活発になることで体がリラックス状態に入れず、睡眠が分断される原因となります。
こうした生活習慣の乱れは、細切れ睡眠だけでなく、慢性的な睡眠不足にもつながる恐れがあります。
睡眠を妨げる疾患の影響
細切れ睡眠は、さまざまな疾患が原因で引き起こされることがあります。
例えば、睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が何度も止まることで睡眠が中断され、細切れ睡眠を招く代表的な疾患です。また、むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)では、足の不快感が原因で夜中に何度も目が覚めてしまうことがあります。
さらに、高齢者に多い夜間頻尿も細切れ睡眠の原因の一つです。頻繁にトイレに起きることで、睡眠が断続的になり、体が十分に休まらない状態を引き起こします。
これらの疾患が疑われる場合は、適切な診療科を受診し、原因を特定することが重要です。治療することで、細切れ睡眠を改善できる可能性があります。
自分が睡眠障害を患っているかどうか気になる方は、下記記事を参考にセルフ診断チェックをしてみましょう。
細切れ睡眠で悩む人ってどんな人?

細切れ睡眠に悩む人には、不規則なシフトワーカーや子育て中のママ、高齢者、睡眠時無呼吸症候群を発症している人などが挙げられます。それぞれの状況や背景を詳しく解説します。
不規則なシフトワーカー
不規則なシフト制で働く人は、細切れ睡眠に悩むことが多いです。
例えば、3交代制(日勤・準夜勤・深夜勤)で働く看護師の場合、日勤で働いた翌日に深夜勤、その翌日に準夜勤、そのまた翌日には日勤があるなど、不規則な勤務体制になります。
その結果、夜に寝る日と朝に寝る日が入り乱れ、生活リズムが非常に崩れやすくなります。特に、深夜勤を終えた後に翌日の日勤に備えて体をリセットするのは難しく、結果として細切れ睡眠に陥りやすくなります。
子育て中のママ
子育て中のママは、細切れ睡眠に悩まされることが多いです。
特に、生まれて間もない赤ちゃんは授乳やおむつ替えのために夜中に何度も目を覚ますことがあり、これに対応するためにママ自身の睡眠は断続的になります。さらに、昼間も家事や育児に追われるため、十分な休息を取ることが難しい状況が続きます。
睡眠時間が短くなってきた高齢者
高齢者は、加齢に伴う体の変化により、睡眠時間が短くなる傾向があります。この原因の一つは、体内時計を調整するホルモン「メラトニン」の分泌量が減少することです。メラトニンは夜間の睡眠を促す役割を果たしますが、加齢とともにその量が減り、眠りが浅くなることがあります。
また、日中の活動量が減少することや、昼寝の時間が長くなることも細切れ睡眠が起こる原因です。
その他、高齢者に多い夜間頻尿も、トイレに行くために夜中に何度も目を覚ますことで、睡眠が分断されてしまいます。このように、さまざまな身体的・生活的な要因が重なり、高齢者はまとまった睡眠を取りづらくなる傾向があります。
睡眠時無呼吸症候群を発症している人
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が何度も止まることで細切れ睡眠を引き起こす代表的な疾患です。呼吸が止まるたびに脳が酸素不足を感知して覚醒状態になるため、睡眠が断続的に中断され、深い眠りに到達しにくくなります。
睡眠時無呼吸症候群の主な原因には、肥満や気道の狭さ、慢性的な鼻づまりなどが挙げられます。いびきが大きい人や寝ている間に息苦しそうな様子が見られる人は、この疾患の可能性があります。また、昼間の強い眠気や突然の居眠り、強い疲労感が特徴的な症状として現れることも多いです。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
大きないびきをかく人と同室で寝ているパートナーも細切れ睡眠になることがある
大きないびきをかく人と同室で寝ている場合、いびきの音が原因でパートナーも細切れ睡眠に陥ることがあります。
睡眠時無呼吸症候群のいびきの音は断続的で非常に大きな音であるため、眠りに入ったとしても何度も目が覚めてしまうことが少なくありません。
こうした状況が続くと、パートナー自身が慢性的な睡眠不足に陥り、日中の疲労感やストレスを感じるようになるでしょう。
細切れ睡眠を繰り返すことで懸念される健康への悪影響

細切れ睡眠自体が病気ではありませんが、を繰り返すと、ストレスの蓄積や体内時計の乱れ、睡眠負債の増加など、健康にさまざまな悪影響を及ぼします。それぞれのリスクを詳しく解説します。
ストレスの蓄積
細切れ睡眠を繰り返すと、十分に体が休まらない状態が続き、ストレスが蓄積しやすくなります。
睡眠は、脳や体をリセットし、ストレスを軽減する重要な時間ですが、断続的な睡眠ではその効果が十分に得られません。その結果、イライラや不安感が増し、さらに睡眠の質が低下する悪循環に陥ることもあります。
体内時計の乱れ
細切れ睡眠を繰り返すと、体内時計が乱れる原因となります。
体内時計は、私たちの睡眠や覚醒、ホルモン分泌、代謝などのリズムを調整していますが、睡眠が断続的に中断されることで、このリズムが崩れてしまいます。その結果、朝起きてもスッキリせず、日中に眠気や疲労を感じやすくなります。
睡眠負債の蓄積
細切れ睡眠が続くと、体が必要とする睡眠が十分に取れない状態が積み重なり、睡眠負債が蓄積します。
睡眠負債とは、慢性的な睡眠不足によって心身に支障をきたしている状態のことで、疲労感や集中力の低下を招くだけでなく、免疫力の低下や生活習慣病のリスクを高める原因にもなります。
また、脳が十分に休まらないため、記憶力や判断力の低下、さらにはメンタルヘルスにも悪影響を及ぼす可能性があります。
睡眠負債を放置すると体に深刻なダメージを与えることがあるため、早めに改善を目指すことが重要です。
睡眠負債について詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください。
細切れ睡眠を改善する6つのポイント

細切れ睡眠を改善するためには、生活習慣や睡眠環境を整えることが重要です。この章では、日常生活に取り入れやすい6つの具体的な改善策を紹介します。
①入浴によって深部体温をコントロールする
睡眠の質を高めるためには、深部体温(体の内側の温度)の調整が重要です。
就寝の1〜2時間前に少しぬるく感じるお湯に浸かることで、深部体温を一時的に上昇させ、その後の自然な体温低下がスムーズな入眠を促します。また、入浴はリラックス効果もあるため、ストレスを軽減し、眠りにつきやすい状態を作ります。
シャワーだけで済ませるよりも湯船に浸かることで、より効果的に深部体温をコントロールすることが可能です。
②就寝前はカフェインやアルコール飲料を避ける
就寝前にカフェインやアルコールを摂取することは、細切れ睡眠を引き起こす原因となります。
カフェインは覚醒作用があり、摂取後数時間にわたって眠気を妨げるため、夜遅くのコーヒーやエナジードリンクは避けた方が良いでしょう。
一方、アルコールは一見眠りやすく感じさせますが、代謝される過程で睡眠が浅くなり、夜中に目が覚める原因となります。
これらを控えることで、体が自然なリズムで睡眠に入れる環境を整えることが可能になるでしょう。
③眠る目的以外で寝床に入らない
細切れ睡眠を防ぐためには、寝床を「眠るためだけの場所」とする意識が重要です。
寝床でテレビを見たり、スマホを操作したりする行動は、脳を覚醒させ、眠りを妨げる原因となります。しかも、こうした行動が続くと、寝床そのものが「眠れない場所」として脳に認識され、細切れ睡眠を悪化させる可能性があります。
寝る目的以外では寝床には入らず、眠気が来て初めて入るようにしましょう。
④朝起きたらカーテンを開けて日光を浴びる
細切れ睡眠を改善するためには、朝起きたらすぐにカーテンを開けて日光を浴びる習慣を取り入れることが効果的です。
日光を浴びることで体内時計がリセットされ、睡眠と覚醒のリズムが整いやすくなります。また、日中に光を多く浴びることで夜間のメラトニン分泌量が増加し、体内時計が調節され、入眠が促進される効果もあります。
毎朝の習慣として取り入れてみましょう。
⑤睡眠時間にこだわらない
細切れ睡眠を解消するには、睡眠時間に必要以上にこだわらないことも大切です。
細切れ睡眠に悩む人ほど、睡眠時間に強くこだわる傾向があります。しかし、「◯時間眠らなければいけない」と考えること自体がプレッシャーとなり、かえって眠りが浅くなる原因になります。
睡眠は時間の長さだけでなく、質も重要です。自分にとって必要な睡眠時間は個人差があり、必ずしも長時間眠ることが良いとは限りません。むしろ、自分の体が自然に必要とする睡眠を尊重し、眠れる時間を有効に活用することが重要です。
⑥昼寝は午後の早い時間帯で30分以内にとどめる
昼寝を上手に活用することで、細切れ睡眠による疲労感を軽減することができます。
ただし、昼寝の時間やタイミングには注意が必要です。昼寝が午後遅くまでずれ込んだり、長時間に及んだりすると、夜の睡眠に悪影響を与え、眠りが浅くなる原因になります。そのため、昼寝は午後の早い時間帯に行い、30分以内にとどめるのが理想的です。短時間の昼寝でも、脳をリフレッシュさせる効果が期待できるとされています。
細切れ睡眠の改善が難しい状況でも効果的に疲れを取る方法は?

現代人の中には、仕事などさまざまな事情で細切れ睡眠をせざるを得ない人もいるでしょう。
しかし、細切れ睡眠が避けられない状況でも、疲労を軽減し睡眠の質を高める工夫は可能です。この章では、やむを得ず細切れ睡眠をする場合でも効果的に疲れを取る方法を紹介します。
シフトワークで働く人
シフトワークで働く人は、不規則な勤務時間により体内時計が乱れやすく、細切れ睡眠になりがちです。特に夜勤の後や勤務が連続する場合、十分に体を休めるのが難しくなるでしょう。
そんなシフトワーカーの方は、仮眠と日光浴をうまく取り入れるのがおすすめです。
①夜勤中に適宜仮眠をとる
夜勤中に適切なタイミングで仮眠を取ることは、細切れ睡眠による疲労を軽減する効果的な方法です。
20〜30分程度の短い仮眠を取ることで、脳がリフレッシュされ、夜勤中の集中力や作業効率アップにつながります。仮眠スペースが確保されていたり、交代で仮眠が取れたりする場合は、積極的に活用しましょう。
効果的な仮眠の方法については下記記事を参考にしてみてください。
②夜勤明けも日勤日と同じように朝に日光を浴びる
夜勤明けには、日勤の日と同じように朝の光を浴びましょう。
夜勤明けは日勤以上に疲れが溜まり、すぐ寝てしまいたくなります。しかしそこで、日勤の日と同じように朝の光を浴びることで、体内時計がリセットされ、昼夜のずれの解消に効果を発揮します。
夜勤後はそのまま昼過ぎまで寝てしまうのではなく、少しでも朝の日光を浴びる時間を確保しましょう。
子育て中のママ
子育て中のママは、赤ちゃんや幼児の夜泣きや授乳のため、まとまった睡眠を取ることが難しい状況にあります。細切れ睡眠が続くことで疲労が蓄積しやすく、日中の活動に支障をきたすことも少なくありません。
その場合は、周りの協力を得ながら、細切れ睡眠の期間を乗り越えることが重要です。
①赤ちゃんが寝たら自分も眠る
赤ちゃんが眠っている間に自分も休息を取ることは、細切れ睡眠を補うために非常に効果的な方法です。
家事や他の作業を優先したくなることもありますが、体力を回復させるためには、自分自身の睡眠を最優先にすることが大切です。短時間でも眠ることで、体や脳の疲労が軽減され、育児への集中力を保つことができます。
②「シフト制育児」を取り入れる
「シフト制育児」とは、家族やパートナーと協力して育児の時間を分担し、お互いに休息を取る時間を確保する方法です。
例えば、夜間の授乳やおむつ替えを夫婦で交代制にすることで、一方が確実に睡眠を確保できるようになります。また、ベビーシッターや地域の育児支援サービスを活用することで、育児の負担を軽減することも可能です。
このように、育児を一人で抱え込まず、チームで協力する仕組みを作ることで、細切れ睡眠による疲労を減らし、育児に向き合う余裕を持つことができるでしょう。
③赤ちゃんの睡眠習慣を整える
赤ちゃんの睡眠習慣を整えることで、細切れ睡眠を減らすことが期待できます。
例えば、睡眠・覚醒リズムの確⽴を助けるために、夜は部屋を暗くし、朝になったらカーテンを開けて部屋を明るくしましょう。また、日中に寝ている間は逆に明るい状態を保ち、生活音なども通常通りにすると、赤ちゃんも「今は昼だな」と感じ、体内時計が大人の時間に次第に合っていきます。
赤ちゃんが安定した睡眠リズムを身につけることで、親の負担も軽減され、より良い睡眠環境を確保することができるでしょう。
睡眠時間が短くなってきた高齢者の場合
高齢者は、加齢による体内時計の変化や日中の活動量の減少により、細切れ睡眠になる傾向があります。その場合は、まずは自分の最適な睡眠時間を知って、それにあったスケジュールを組むことが大切です。
①自分にとって最適な睡眠時間を知る
高齢者の場合、若い頃と比べて必要な睡眠時間が短くなることがあります。
そのため、一般的な「7〜8時間」という目安にとらわれず、自分にとって無理なく体が回復する睡眠時間を見極めることが大切です。起床後にスッキリと目覚め、日中に眠気や疲労感を感じない程度の睡眠が最適とされます。
まずは睡眠日記をつけるなどして、どれくらいの睡眠時間が自分に合っているのかを確認するところから始めましょう。
②社会生活と大幅にずれないように逆算して睡眠スケジュールを組む
高齢者が細切れ睡眠を効果的に管理するには、自分に必要な睡眠時間を把握したうえで、社会生活のリズムと大きくずれないように睡眠スケジュールを組むことが重要です。
例えば、朝の活動や家族の生活スケジュールに合わせて起床時間を固定し、それに基づいて就寝時間を逆算して設定します。これにより、昼夜のリズムが整い、体内時計が安定しやすくなります。
また、昼寝の時間もこのスケジュールによって管理することで、夜に寝つきが悪くなる状態を防ぎ、昼夜のタイミングと大幅にずれた細切れ睡眠にならずに済むでしょう。
このように、日常生活に調和したスケジュールを維持することが、高齢者にとって理想的な睡眠環境の確保につながります。
病気によって細切れ睡眠になっている場合はクリニックを受診しよう

細切れ睡眠の背景には、睡眠時無呼吸症候群(SAS)や不眠症などの疾患が隠れている場合があります。この章では、細切れ睡眠と病気との関係と、クリニックでの治療の重要性について解説します。
細切れ睡眠は不眠症の症状のひとつ
不眠症は、長期間にわたって「眠れない」「寝つきが悪い」などの症状が続き、さまざまな不調が現れる疾患です。
そして、不眠症は下記のような症状が特徴で、細切れ睡眠はこの中の中途覚醒に近い症状です。
- 入眠障害(寝つきが悪い)
- 中途覚醒(眠りが浅く途中で何度も目が覚める)
- 早朝覚醒(早朝に目覚めて二度寝ができない)
こうした不眠症はストレスや生活習慣の乱れ、加齢などが要因となることが多く、睡眠が断続的に中断される状態が続くと、疲労や体調不良を招きやすくなります。
不眠症について詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
細切れ睡眠に加えていびきをかいている人は睡眠時無呼吸症候群の可能性あり
細切れ睡眠に加え、大きないびきを伴う場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。
いびきは気道が狭くなっているサインであり、日常的にいびきをかいている場合はかなり進行している可能性があります。
そして、睡眠時無呼吸症候群が慢性化すると毎晩細切れ睡眠になることで睡眠の質が著しく低下し、日中の強い眠気や集中力の低下などを引き起こし、社会生活に大きな悪影響を及ぼします。
睡眠時無呼吸症候群の症状について詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
睡眠時無呼吸症候群を発症すると命に関わる合併症を引き起こすことも
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、適切に治療しないと命に関わる合併症を引き起こす危険な疾患です。
呼吸が断続的に止まることで体内が慢性的な酸素不足に陥り、高血圧や心疾患、脳卒中などのリスクが大幅に増加します。また、糖尿病や肥満の悪化を招くこともあります。
さらに、睡眠不足による集中力の低下や疲労感が続き、日中の事故や怪我のリスクも高まります。
このように睡眠時無呼吸症候群は健康全般に影響を及ぼす疾患であり、早期に診断し、治療を受けることが極めて重要です。早期治療の重要性について、下記記事も併せてご覧ください。
クリニックで治療を受けることが細切れ睡眠を早期改善する近道
細切れ睡眠の改善には、専門のクリニックで適切な診察と治療を受けることが近道です。
不眠症でクリニックを受診すると、睡眠薬などの薬物療法や生活習慣の改善、そして認知行動療法など、さまざまな方法を用いて多方面から不眠の解消を後押しします。
<不眠症に対応している精神科・心療内科「新宿うるおいこころのクリニック」についてはこちら>
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の場合は、睡眠ポリグラフ検査や問診を通じて正確な診断が行われます。治療には、CPAP(シーパップ)療法やマウスピース治療などが症状に応じて提案されるため、自分に合った方法で細切れ睡眠の改善を進めることができます。
睡眠の問題は、さまざまな要素が複雑に絡み合って起きていることも多いです。自己流で対処しようとせず、専門家に頼ることが細切れ睡眠をより早く改善する方法となるでしょう。
いびきメディカルクリニックでは切らない いびきレーザー治療「パルスサーミア」で根本改善を目指せる
より早く、より痛みを抑えたいびき治療を希望する方には、切らない いびきレーザー治療「パルスサーミア」をおすすめします。
パルスサーミアは、いびきメディカルクリニックで実施しているいびきレーザー治療で、痛みを最小限に抑えながら、喉粘膜の広がりを解消し、いびきの根本改善を目指すことができます。
ダウンタイムもほぼないので、日常生活への影響も少ないです。気になる方は、ぜひいびきメディカルクリニックへご相談ください。
<いびきメディカルクリニックのいびきレーザー治療「パルスサーミア」の詳細はこちら>
細切れ睡眠は体への負担が大きい!早期の改善を目指しましょう
細切れ睡眠は、心身に大きな負担を与え、健康リスクを高める原因となります。
生活習慣や睡眠環境を整え、必要に応じて専門医の診察を受けることで、改善が期待できます。いびきや無呼吸が原因の場合は、適切な治療が根本的な解決への近道です。
快適な眠りを取り戻し、健康的な生活を目指しましょう。
よくある質問
細切れ睡眠が定着すると、ストレスの蓄積や体内時計の乱れ、そして睡眠負債が蓄積してさまざまな不調を体にもたらします。