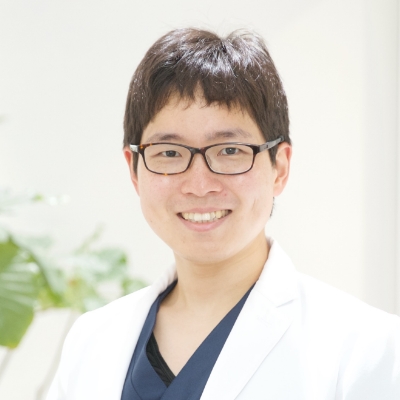睡眠障害にはどんな種類がある?睡眠障害の原因と対策を解説!
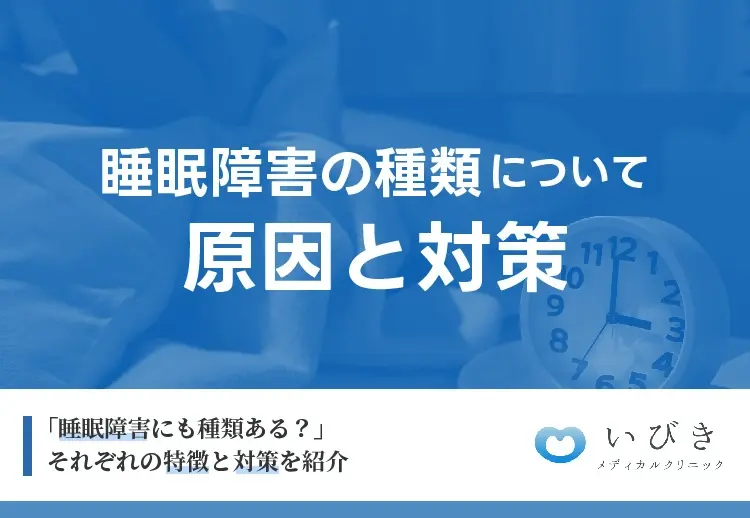
「最近なんだか眠れない…」
「寝ても寝ても疲れが取れない…」
「もしかして睡眠障害なのかも?」
この記事にたどり着いた方は、眠りに関するお悩みを抱えているのではないでしょうか?睡眠は健康維持に重要な要素のひとつです。十分に眠れなかったり、寝ても心身が回復しない場合は、睡眠障害の可能性があります。睡眠障害は心身に重大な影響を与え、生活に支障をきたします。
そこでこの記事では、不眠症や過眠症、ナルコレプシーなどをはじめとした睡眠障害の種類や原因、対策について解説します。
目次
睡眠障害とはどんな病気?

睡眠障害とは、十分な睡眠を得られずに日常生活に支障をきたす病気の総称です。不眠症、睡眠時無呼吸症候群、過眠症、レム睡眠行動障害などが挙げられます。
睡眠障害は、ストレスや生活習慣の乱れ、身体的な疾患などさまざまな要因によって引き起こされます。睡眠障害が続くと、日中の眠気や集中力の低下、心身の健康への影響が懸念されるため、早期の受診や治療が必要です。
睡眠障害のおもな種類

睡眠障害には多くの種類があり、その症状や原因によって分類されます。ここでは睡眠障害のおもな種類を紹介します。
不眠症
不眠症は、布団に入っても眠れない、寝付きが悪い、途中で目が覚めやすい、早朝に目が覚めてしまうなどの症状が特徴です。ストレスや不規則な生活習慣、心身の疲労などが原因とされます。
短期的な不眠は自然に改善しますが、長期化するにつれ、専門医による適切な治療が不可欠といわれています。
不眠症の種類1.入眠困難
夜、布団に入ってもなかなか眠くならず、入眠までに30分以上かかる状態です。ストレスや過度の緊張、不安などがおもな原因です。
不眠症の種類2.中途覚醒
眠りについたものの、夜中に何度も目が覚める状態のことです。睡眠の質が低下し、翌日の眠気や集中力低下につながる可能性があります。
中途覚醒についての詳細は下記記事をご覧ください。
不眠症の種類3.早朝覚醒
予定より早く目が覚めてしまう、いつもより2時間以上目が覚めてしまう不眠症のひとつです。結果的に睡眠時間が不足し、疲労感や不満足感を引き起こしてしまいます。
早朝覚醒についての詳細は下記記事をご覧ください。
不眠症の種類4.熟眠障害
常態的に眠りが浅い症状で、睡眠時間に対して疲労回復が期待できません。深い眠りが得られないため、翌日の体調や集中力に影響を与える心配があります。
過眠症
過眠症は、過剰な睡眠欲求や昼間の過度な眠気を特徴とする状態です。夜間の睡眠時間が充分でも、日中に眠気を感じることがあります。
自動車の運転中や工業用機械の操作中に、我慢できないほどの眠気に襲われると、交通事故や業務上の過失事故を起こすリスクが高まるため、注意が必要です。
過眠症の詳しい情報については、こちらの記事が参考になります。
特発性過眠症
特発性過眠症は、睡眠時間が通常よりも長くなり、日中に何度も居眠りをする症状が見られる疾患です。昼寝が1時間以上にわたる場合もありますが、目が覚めてもスッキリした感覚がなく、ぼーっとした状態が続きます。
めまいや立ちくらみ、頭痛などの自律神経症状で悩まされる方も多く、日常生活に支障をきたします。とくに10~20代の若年層に多く見られますが、原因は解明されていません。
ナルコレプシー
ナルコレプシーは、突然の睡魔や昼間の居眠り、睡眠中の筋肉の弛緩などを特徴とする睡眠障害です。夜間に十分な睡眠をとっていても、日中の眠気は解消されません。特発性過眠症とは異なり、昼寝は短めの30分以内。起床後は一時的にスッキリするといわれています。
授業中に居眠りをしてしまうため「やる気がない、不真面目だ」と評価される学生さんがいらっしゃいます。薬物療法や生活習慣の見直しで改善する可能性があるため、心当たりがある場合は早めに受診しましょう。
概日リズム睡眠覚醒障害
概日リズム睡眠覚醒障害は、睡眠と覚醒のリズムが正常と異なるパターンを持つ睡眠障害です。通常は24時間のリズムに合わせて眠りや覚醒が起こりますが、この障害では生活リズムが乱れます。日中に眠気を感じたり、夜間に眠れない状態が続いたりして、日常生活に支障をきたします。
睡眠関連運動障害
睡眠関連運動障害は、睡眠中や睡眠前後に単純で同じような動きをする症状が特徴です。レストレッグス症候群や周期性四肢運動異常症などのように、自分の意志ではなく、勝手に身体が動くものです。そのため、入眠困難や睡眠の質低下に悩まされます。
熟睡できないため、疲労回復を妨げたり、ストレスを蓄積させたりする原因です。
睡眠時随伴症
睡眠時随伴症は、睡眠中の移動行動を特徴とした睡眠障害です。いわゆる「寝ぼけ行動」のことで、急に大声を出したり泣き出したりする夜驚症、寝ながら食事をする夜間食事障害などがあります。暗闇の中を歩いて転倒したり、寝ている家族を叩いたりするなどの行動を起こすため、安全性の確保が必要です。
睡眠呼吸障害
睡眠呼吸障害は、睡眠中に呼吸が乱れる状態を指します。とくに、30~60歳代の男性に多いといわれています。十分な睡眠時間を確保していても、疲労が回復できないため、朝の起床を辛く感じやすいでしょう。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に一時的に呼吸が止まる症状です。これにより、酸素が体内に供給されず、血中酸素濃度が低下します。
おもな症状には、大きないびきや繰り返し起こる呼吸停止が挙げられます。放置すると高血圧や心臓病などの合併症を引き起こす可能性があるため、早期の治療が必要です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください。
睡眠障害の原因はさまざま
睡眠障害を発症する原因は多方面からの影響が考えられます。原因を探る際は、視野を広げて考えてみましょう。
心理的ストレス
心理的ストレスは、睡眠障害の主要な原因のひとつです。ストレスが長期間続くと、交感神経が優位になり、入眠困難や睡眠の浅さを引き起こすことがあります。
ストレスを皆無にした生活は不可能に近いですが、極力取り除くようにライフスタイルを変えたり、ストレスを上手に発散したりする工夫も必要です。
生活リズムの乱れ
不規則な生活リズムや夜間の活動、スマートフォンやパソコンの使用なども、睡眠の質を低下させる要因です。職種によっては、夜勤や交代勤務などで規則的な生活を送れないケースもあるでしょう。部署移動や転職も視野に入れる必要があるかもしれません。
スマートフォンやパソコンなどの使用は寝る数時間前に中止する、寝室には持ち込まないなどの工夫も有効でしょう。
薬やアルコール、タバコの作用
一部の薬物やアルコール、タバコには、睡眠に影響を与える作用があります。とくに、就寝前の摂取や服用は、睡眠の質を低下させる可能性があります。アルコールやタバコとの付き合い方を見直し、必要であれば禁酒や禁煙に挑戦してみましょう。
睡眠障害(不眠症)セルフチェック診断
睡眠障害(不眠症)のセルフチェックは、自分の睡眠状態を客観的に評価するための手段です。以下の質問に「はい」または「いいえ」で答えてみてください。
これらの質問に3つ以上「はい」と答えた場合、不眠症の可能性があります。しかし、自己診断だけでは確定できません。症状が続く場合は、医師や専門家の診断を受けましょう。
睡眠障害(不眠症)は自力で治す?セルフケアと対策

不眠症の症状が軽い場合は、自分で治せる場合があります。以下は睡眠障害(不眠症)のセルフケアと対策の一例です。
睡眠時間へのこだわりを捨てる
適切な睡眠時間は人それぞれ異なります。「毎日8時間寝なくては」とこだわると、反対にストレスを増やす原因です。日中に眠気がなければ、とくに心配はありません。6時間睡眠が適しているショートスリーパーの方もいらっしゃいます。
自分に最適な睡眠時間や、睡眠のリズムを把握することは、健康的な生活を送る第一歩です。
ストレス管理とリラックスタイムの導入
過度なストレスは不眠症の原因になります。多忙な毎日の中でも、趣味やリラックスする時間を大切にしましょう。友人との会話や、好きなことに集中する時間は、日々の雑踏を忘れさせてくれます。ストレスが軽減すれば睡眠の質が良くなり、熟睡が期待できるでしょう。
健康的な生活習慣
適度な運動や健康的な食生活を心がけることも重要です。運動で身体的な疲れを感じると、自然に眠りにつける可能性があります。気持ちの良い汗を流すスポーツは、ストレス発散にも有効です。また、寝る前には読書やストレッチなどで、リラックスできる時間を過ごしましょう。
睡眠障害(不眠症)の病院における診断方法と治療法

不眠症の診断と治療は、おもに睡眠専門医や精神科医によっておこなわれます。
まずは症状についての詳細なヒアリングです。睡眠パターンや日中の症状などを詳しく聞き、全体像を把握します。場合によっては、睡眠日誌の記録を提案されるでしょう。毎日の就寝時間、起床時間、睡眠の質や量などを記録すると、傾向と対策に役立ちます。
睡眠日誌の内容から必要があると判断された場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニングテストや睡眠ポリソムノグラフィ(PSG)が実施されます。PSGとは、睡眠中の脳波や心拍数、筋肉の動き、呼吸などを、機械を使って記録する診断方法です。これにより、睡眠の質や異常を検知できます。
その後、症状に合わせた治療方法へと進みます。睡眠の環境や生活習慣を改善する方法を指導されたり、睡眠薬が処方されたりします。ストレスや心理的な問題がある場合は、根本的な解決をするためのカウンセリングや認知行動療法を提案される可能性もあるでしょう。
不眠症の治療法は個人によって異なります。症状や原因に合わせて、最適な治療法を医師と相談して選択してください。
なおこちらの記事では、睡眠の質をセルフチェックできます。睡眠障害の原因に思い当たる節がない方は、ぜひ参考にしてください。
睡眠障害は病院の何科を選べば良い?
睡眠障害に悩んでいる場合に診断や治療を受けるためには、適切な医療機関を選ぶことが重要です。とはいえ、これまで睡眠に関する受診の経験がないと、どのような病院を探せばよいか迷ってしまいますよね。
睡眠障害を専門的に診断し、治療する科としては、おもに精神科・心療内科と睡眠外来が挙げられます。
精神科・心療内科
精神科や心療内科は、睡眠障害の診断や治療に関する専門知識を持っています。精神的な要因が睡眠障害に関与している場合、こちらを受診すると良いでしょう。カウンセリングによるストレス解消へのアプローチや、物事のとらえ方なども相談できます。
新宿うるおいこころのクリニックでは、不眠症などの精神科・心療内科が診療科目である睡眠障害に関する治療を行っています。詳しく知りたい方は公式HPからご確認ください。
睡眠外来
一部の病院やクリニックでは、睡眠外来という専門の診療部門があります。睡眠障害に特化した専門医が在籍しており、専門機器を用いた診断や治療ができます。睡眠外来を受診すると、より専門的なアプローチで睡眠障害を改善できるかもしれません。
睡眠外来について詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください。
いびきに関するお悩みは、いびきメディカルクリニックへご相談ください
睡眠障害は不眠症や睡眠時無呼吸症候群など、充分な眠りを得られない病気の総称です。それぞれ症状や自覚症状の有無、生活への影響度が異なり、原因や治療法もさまざまです。
適切な検査や治療には専門医の診察が不可欠であるため、信頼できるクリニックを受診しましょう。
いびきメディカルクリニックでは、いびきに関するお悩みに対応しております。いびきや無呼吸にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
よくある質問
まずは原因を取り除く工夫をしましょう。ストレス発散や運動不足を解消するだけで、薬に頼らず眠れるようになる方も多くいらっしゃいます。寝室の環境整備や寝る前の過ごし方も重要です。リラックスして寝床につけるよう、夜のルーティンを見直してみましょう。