睡眠不足(寝不足)が続くとどうなるか?解消する4つポイントを解説!
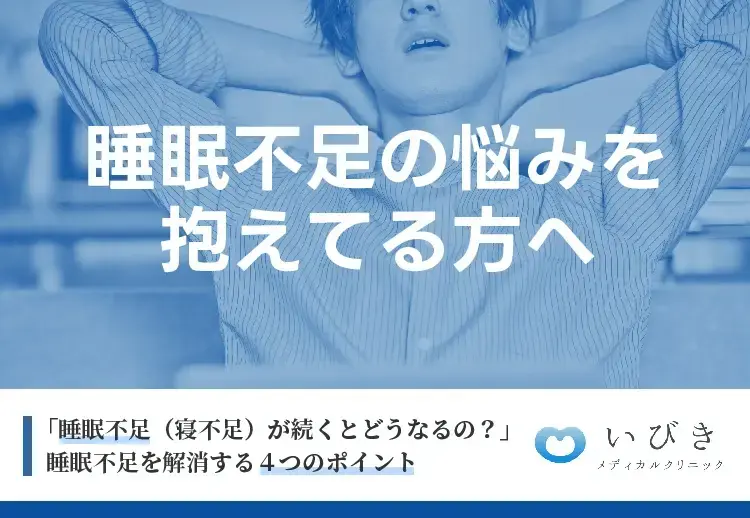
「睡眠不足(寝不足)が続くとどうなるの?」
「睡眠不足ってどうして起こるの?」
「睡眠不足を解消する方法を知りたいな…」
と考えている方も多いのではないでしょうか。
睡眠には心身をメンテナンスする役割があります。そのため、睡眠不足が続くと、さまざまな病気のリスクになったり、仕事や勉強のパフォーマンスが低下したりします。睡眠不足を解消するためには、適切な睡眠時間を知る、質の良い睡眠を取るなど4つのポイントを有効活用しましょう。
この記事では、睡眠が必要な理由、睡眠不足(寝不足)が続くとどうなるか、体に与える影響、睡眠不足の原因、睡眠不足を解消するポイントについて解説します。
目次
睡眠が必要な理由とは?

皆さんは、人間を含む動物が、なぜ睡眠を取るのか知っていますか。ここでは、睡眠について、以下の2つについて解説します。
- 睡眠の役割は心身のメンテナンス
- 睡眠に関与する2つのシステム
まず、睡眠の基本を知ると、より詳しく理解できるようになります。
睡眠の役割は心身のメンテナンス
心身をメンテナンスするために取るのが睡眠です。睡眠中、私たちの体の中では、脳や内臓、自律神経系などその日に起きた体内の不具合をリセットする作業が行われています。これは、翌日も無事に活動できるように備えるための、大切な整備の時間です。
おもに、以下の作業をしています。
- 記憶を整理する
- 疲労を回復する
- 免疫力を向上させる
- 自律神経のバランスを整える
- 食欲をコントロールする
記憶を整理する
睡眠中の脳は、学習した記憶を整理し、必要な情報を定着・強化する一方で、老廃物を脳脊髄液中に捨てる作業もしています。「アミロイドβ」というたんぱく質は、脳脊髄液中に流れていく老廃物のひとつ。老廃物であるアミロイドβが、排出されることなく脳に蓄積することがアルツハイマー病の原因ともいわれています。睡眠不足になると、老廃物の排出などによるメンテナンスがうまくできことで、認知症発症リスクが増加することがわかっています。
疲労を回復する
睡眠中にはたくさんのホルモンが分泌されていて、その分泌のパターンも、心身のメンテナンスに大きく関わっています。たとえば、次のような働きのホルモンがあります。
- <成長ホルモン>
分泌されるタイミング:睡眠直後
働き:筋肉や骨、内臓などの傷ついた部位の修復による疲労回復 - <メラトニン>
分泌されるタイミング:眠りの前半
働き:抗酸化作用による、がんや老化などの予防 - <コルチゾール>
分泌されるタイミング:起床前から日中の活動
働き:抗炎症作用や免疫抑制、代謝促進などの働き
人間にとって必要不可欠な働きをするホルモンが、睡眠不足によって分泌のリズムが乱れると、心身不調の原因になる可能性があるのです。
免疫力を向上させる
免疫システムで感染やがん細胞関与するT細胞が活躍するのは、夜間です。睡眠期前半に多く分泌されるメラトニンがT細胞産生に関与しているので、しっかり眠っていないと免疫システムも十分な働きを示せません。
自律神経のバランスを整える
自律神経には、日中に優位の「交感神経」と睡眠中に優位の「副交感神経」があり、交互に働きます。睡眠不足になると、交感神経優位の状態が続くことなり、身体活動が不調、本来の力を発揮できなくなってしまいます。
食欲をコントロールする
睡眠不足になると脂肪細胞から分泌される食欲抑制するホルモン「レプチン」が減少し、胃から分泌される食欲増進ホルモン「グレリン」が増えます。徹夜が続いて、スナック菓子やこってりした甘いものが食べたくなった経験はありませんか?これは、食欲ホルモンバランスの乱れによって起るので、生活習慣病発症するリスクが高まります。
睡眠に関与する2つのシステム
睡眠のメカニズムには、次の2つのシステムが関与していることが知られています。
- 体内時計機構
- 恒常性維持機構
体内時計機構とは、毎日決まった時刻にホルモンが分泌されたり、体温が上下したりして、それらの影響で自然に、夜になると眠くなり、朝になれば目覚めます。もう1つの恒常性維持機構とは、時間の経つと疲れて眠くなり、眠れば回復して目覚めます。日中の活動による心身の疲れを回復させるシステムのことです。
2つのシステムが車の両輪のように一緒に働くことで、毎日の睡眠と覚醒がうまく保たれていると考えられています。片方が不調だと、日々の睡眠・覚醒に問題が出てきてしまいます。
参考:
眠りのメカニズム | 厚生労働省
睡眠不足(寝不足)が続くとどうなるか:体に与える影響

ここでは、睡眠不足(寝不足)が続くと、体にはどんな影響があるかについて、以下の4つを解説します。
- さまざまな病気のリスクになる
- 仕事や勉強のパフォーマンスが低下する
- メンタル面に問題が出てくる
- 事故のリスクが増える
知っておくと、しっかり睡眠を取ることの大切さを実感できます。
さまざまな病気のリスクになる
睡眠不足はホルモン分泌や自律神経機能に大きな影響をおよぼします。一例が上記の食欲ホルモンです。実際に慢性的な睡眠不足状態にある人は、高血圧や糖尿病、心筋梗塞や狭心症などの冠動脈疾患という生活習慣病に罹りやすいといわれています。
仕事や勉強のパフォーマンスが低下する
睡眠不足の経験がない人はいないのではないでしょうか。しかし、睡眠不足は続いてしまうと、仕事や勉強などで、以下のようなことが起きると言われています。
- ケアレスミスが増える
- 集中力が低下して時間がかかる
- 健康を損なうので、遅刻や欠席・欠勤が増える
勉強や仕事が理由の睡眠不足であったとしても、逆に効率が悪くなることにつながります。
メンタル面に問題が出てくる
睡眠不足だと、ちょっとしたことで怒る、不機嫌になる、いらいらするなど、精神症状にも支障がでます。中高校生であれば情緒不安定になるので、不登校につながる可能性もあるでしょう。
仕事や勉強上のミスが重なる、慢性的に疲れているなどの理由で、精神的にも不安定になり、ネガティブな思考になりやすくなります。その結果、うつ症状が起きる可能性もあります。
事故のリスクが増える
睡眠不足だと、どうしても疲労が蓄積し、集中力が低下してしまうので、自動車や機械などの運転には危険が伴います。
実際に、慢性不眠症者では産業事故リスクが一般人に比べて7倍高く、交通事故リスクは一般人2%であるのに対し、慢性不眠症者では5%に上ると報告されています。
参考:
睡眠不足に起因する事故の防止と健康起因事故の防止について|国土交通省自動車局安全政策課
睡眠不足の原因は睡眠時無呼吸症候群やいびきかもしれない

最近、仕事や勉強で睡眠不足の自覚がある人はともかく、
「心当たりがないのに、何となく、眠い…」
そのような方の睡眠不足の原因は、ひょっとしたら、睡眠時無呼吸症候群やいびきかもしれません。
ここでは、睡眠時無呼吸症候群について、以下のことを解説します。
- 睡眠時無呼吸症候群とは
- 睡眠時無呼吸症候群の症状
- 睡眠時無呼吸症候群になりやすい人
自分に当てはまるかどうか、チェックしながら読んでみましょう。
睡眠時無呼吸症候群とは
睡眠時無呼吸とは、睡眠中に呼吸が10秒以上停止する状態のことで、睡眠時無呼吸症候群とは、1時間あたり5回以上無呼吸が発生し、そのためによく眠れず、日中に異常な眠気を催す状態のことです。主な症状の一つにいびきがあります。
睡眠時無呼吸症候群には、以下の3つの種類があります。
- 中枢型:脳や神経、心臓の病気が原因
- 閉塞型:のどが閉じることが原因
- 混合型:中枢型と閉塞型が混合して起こるタイプ
閉塞型が最も多く、肥満と強い関係がありますが、肥満でなくとも起こる場合があります。
睡眠時無呼吸症候群とは何かについて知りたい方は下記記事をご覧ください。
睡眠時無呼吸症候群の症状
睡眠時無呼吸症候群の症状として挙げられるものは、以下のものです。
- 日中の眠気
- いびき
- 頻回の覚醒(睡眠中に何度も目覚める)
- 起床時の頭痛やだるさ、むくみ
- 不眠、気分が沈む(うつ状態)
- 性格の変化
- 幻覚
- 性機能障害
自覚症状として多いのは日中の眠気、家族など周囲からの指摘では、いびきがあります。
睡眠時無呼吸症候群の症状について詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください。
睡眠時無呼吸症候群になりやすい人
睡眠時無呼吸症候群になりやすい人の特徴は、以下の通りです。
- 生活習慣病にかかっている人
- 太っている人
- 顎が小さいか後ろに引っ込んでいる人
- 女性よりも男性
睡眠時無呼吸症候群になりやすい人の特徴については下記記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
生活習慣病にかかっている人
生活習慣病にかかっている人は、睡眠時無呼吸症候群を発症しやすい傾向にあります。たとえば、喫煙をすると、咽喉頭部に炎症をもたらす恐れがあり、また、飲酒や睡眠薬の服用、過労は咽頭筋肉の緊張を低下させる可能性があります。これらは、気道の閉塞を引き起こし、睡眠時無呼吸症候群になる大きな要因になります。
太っている人
肥満の人は軟口蓋や喉にも脂肪がついているため、睡眠時には上気道が狭くなりやすい傾向にあります。このような、肥満体型の人も睡眠時無呼吸症候群を発症する可能性が高くなるため注意が必要です。特に、体重が急激に増加した人や、学生時代より10㎏以上太った人はダイエットを検討しても良いでしょう。
顎が小さいか後ろに引っ込んでいる人
顎が小さい、喉が狭いなど骨格に特徴や異常がある人や、アデノイドなどの顎が引っ込んでいる人は、そうでない人より気道が狭くなりやすいため、睡眠時無呼吸症候群になる可能性が高くなります。
女性よりも男性
性別では、男性がかかりやすく、女性の約2〜3倍の発症率といわれています。性差がある理由の一つは太り方です。太った場合、男性は脂肪が上半身につきやすく、顎や喉へ蓄積しやすいですが、女性は下半身につきやすいため、発症率は下がります。しかし、閉経後、女性ホルモンが低下すると、男性と同程度なりやすくなるので注意が必要です。
これらの特徴がある場合は、睡眠時無呼吸症候群を発症していないか検査してみることをおすすめします。また、上記の特徴が気になる方は、生活習慣を見直し、適正体重を維持しましょう。
参考:
睡眠時無呼吸症候群になりやすい人とは|運輸・交通SAS対策支援センター
睡眠不足を解消する4つのポイント

睡眠不足(寝不足)が続くと、体によくない影響が起きてしまいます。そのような事態を防ぐため、ここでは、睡眠不足を解消する4つのポイントについて、解説します。
- ポイント1. 自分に適切な睡眠時間を知る
- ポイント2. 質の良い睡眠を取る
- ポイント3. 光とストレスをコントロールする
- ポイント4. 短時間睡眠を活用する
できることを、今日から取り入れてみましょう。
ポイント1. 自分に適切な睡眠時間を知る
自分に適切な睡眠時間は、次のような方法で分かります。
- 睡眠時間を決め、休日も同じ睡眠時間で1週間ほど生活する。
- 次の週は15~30分くらい睡眠時間を延ばし、日中の調子の変化など確認する。
- さらに15〜30分ほど睡眠時間を延長して、1週間ほど過ごす。「これ以上眠れない」と感じた場合は、睡眠時間を少し短くする。
- 上記を繰り返し、調子よく過ごせる睡眠時間の長さを見極める。
例えば、6時間睡眠の方であれば、睡眠時間を6時間半にして1週間過ごします。6時間半にしても、日中、眠気や不調を感じる場合は、7時間に伸ばしてみます。睡眠時間を延長していく中で、夜中に目覚める、早朝に目が覚めることが出てきたら、睡眠時間が長すぎるサインです。「これ以上は眠れない」時間を見つけたら、15〜30分くらい短くして、最も心地よく過ごせる睡眠時間を見つけてみましょう。
ポイント2. 質の良い睡眠を取る
質の良い睡眠を取るために、以下のことをしてみましょう。
- 規則正しい生活をする
- 運動習慣を持つ
- 就寝の2~3時間前に入浴する
質の良い睡眠は、規則正しい睡眠習慣から始まります。というのは、体内時計が、睡眠のタイミングだけでなく、ホルモン分泌や生理的活動を調節して睡眠に備えてくれているからです。体内時計は自分の意志ではコントロールできないので、規則正しい生活こそが、睡眠をスムーズに行うコツなのです。
国内外の疫学研究で、運動習慣を持っていると不眠になりにくいことがわかっています。とくに睡眠の維持に効果があるようです。習慣的に激しくない運動を続けることが重要です。寝付きがよくなり、深い睡眠が得られるようになるでしょう。早足の散歩や軽いランニングなどの有酸素運動がおすすめです。
タイミングも考慮できるのであれば、就寝の数時間前がいいでしょう。運動で脳の温度を一過性に上げると、就寝時の脳温の低下量が運動しないときより大きくなります。ただし、就寝直前は体を興奮させるので禁物です。
入浴が質の良い睡眠に役立つのは、運動と同様に、就寝前に一時的に体温をあげるからです。深い睡眠のためには就寝直前が良いといわれていますが、寝付きが悪くなる可能性があります。寝つきを優先させると、就寝2~3時間前の入浴がおすすめです。自分の体調や好みに合わせて、入浴しましょう。
参考:
快眠と生活習慣|厚生労働省
ポイント3. 光とストレスをコントロールする
体内時計を24時間に調節するために、起床後、すぐにカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。人間の体内時計周期は24時間より長めなので、毎日、リセットしないと生活がどんどんずれてしまいます。朝の光には時計を早める働きがあります。
嫌な夢は目覚めを悪くする原因の一つ。悪夢を見ないように、ストレスコントロールすることも必要です。寝る直前に見たり、考えたりすることがストレスになり、悪夢をみるきっかけになる可能性もあります。寝る前にはネガティブなことを考えないことも大切です。
ポイント4. 短時間睡眠を活用する
仕事や生活上の都合で、どうしても夜間に十分な睡眠時間を確保できなかった場合には、短時間睡眠を活用してみましょう。目覚めた後、作業能率がアップすることが報告されています。ただし、必要以上に長くいと、目覚めの悪さを感じるので、30分以内にとどめるのがいいでしょう。
睡眠不足による睡眠時無呼吸症候群やいびきにお悩みならいびきメディカルクリニックにご相談ください
今回は、睡眠不足(寝不足)が続くとどうなるかについて解説してきました。睡眠には心身をメンテナンスする役割があります。そのため、睡眠不足が続くと、さまざまな病気のリスクになったり、仕事や勉強のパフォーマンスが低下したりします。睡眠不足を解消するためには、ポイントを押さえて、質の良い睡眠を取ることが必要です。
最後に、「睡眠不足の原因は、睡眠時無呼吸症候群やいびきが原因かもしれない」と悩んでいる方には、いびきメディカルクリニックをおすすめします。
いびきメディカルクリニックは、いびき・無呼吸治療の専門医院です。無料カウンセリングも実施していますので、お気軽にご相談ください。
よくある質問
日本の成人の標準的な睡眠時間は6時間以上8時間未満と考えられています。睡眠時間は年齢や季節に応じて、日中の眠気で困らないくらいであれば、十分といっていいでしょう。必要以上に長く睡眠時間をとっても、健康になるわけではありません。





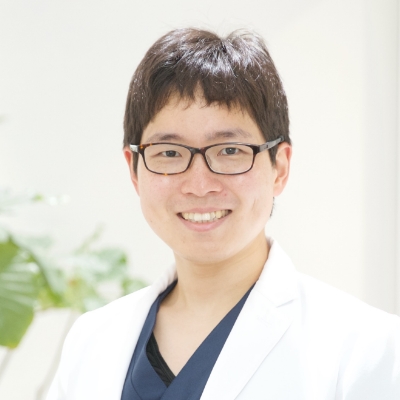


になりやすい人の特徴は?原因や治療・治し方について-150x150.webp)