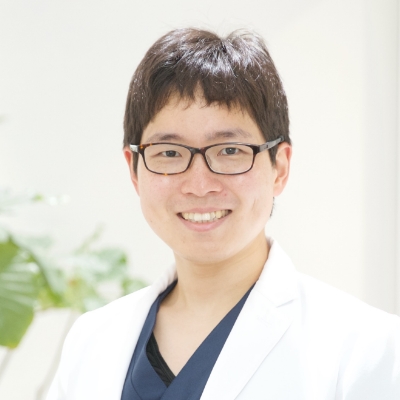睡眠時無呼吸症候群の顔つきに特徴はある?見た目でわかる兆候を解説
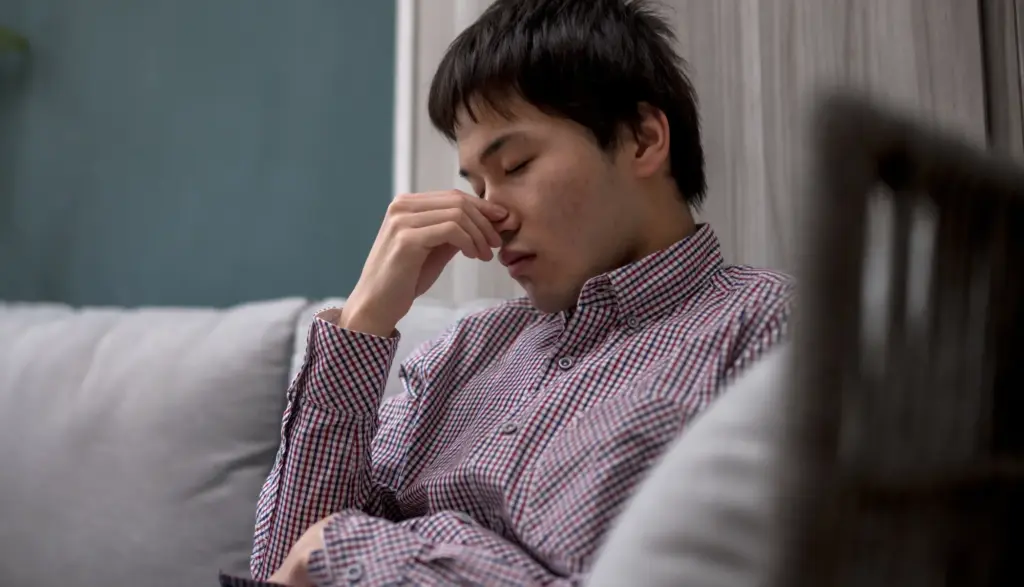
「睡眠時無呼吸症候群の人には顔つきに特徴がある」と聞いたことはありませんか?
実はこの病気は、呼吸だけでなく、顔の輪郭や顎の発達など“顔つきの変化”にも影響を及ぼすことがあります。
睡眠中の無呼吸やいびきを放置すると、成長や見た目にまで関わるリスクがあります。顔つきの特徴に気づくことが、早期発見・早期治療への第一歩になるかもしれません。
この記事では、睡眠時無呼吸症候群による顔つきの特徴や、似た症状が現れる他の病気についても解説します。
目次
睡眠時無呼吸症候群の人は顔つきに特徴がある

睡眠時無呼吸症候群の恐れのある人の顔つきには特徴があり、重症のまま放置していると命に関わることもあります。
まずは睡眠時無呼吸症候群について解説します。
睡眠時無呼吸症候群とは
睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に10秒以上の呼吸停止が1時間あたり5回以発生し、このことが原因で熟睡できず、日中に異常な眠気を催す状態のことです。ほとんどの場合、いびきを伴います。睡眠時無呼吸症候群には、中枢型や閉塞型、両者の混合タイプの混合型がありますが、最も多いのは閉塞型です。閉塞型は肥満と強い関連があるといわれています。
睡眠時無呼吸症候群は、多くの場合、舌や扁桃、口蓋垂などが気道をふさぐことで起こります。舌や扁桃、口蓋垂などが気道をふさいでしまう原因は以下の通りです。
- 太っている
- 顔面骨格・下顎骨が小さい
- 上気道・咽頭部の変形・軟部組織が大きい
太って、首やあごまわりに余分な脂肪がつくと、どうしても気道はふさがりやすくなります。欧米では、一番の原因は肥満だともいわれています。
顔面骨格構造が全体的に小さかったり、下顎が小さかったりすると、もともと気道が狭いので、ふさがりやすい状態です。この状態であれば、体重が少し増えただけでも、睡眠時無呼吸症候群になるリスクが高まってしまうでしょう。
日本人を含む東アジア人は、特徴的な構造「顔面に凹凸が少なく平らで厚みがない、上顎に比べて下顎が小さい」ために、睡眠時無呼吸症候群になりやすいともいわれています。
鼻腔の空気の通行を障害する原因に、鼻中隔弯曲症や肥厚性鼻炎、アデノイド肥大、鼻茸などがあります。また、のどの空気の通りを障害する、アデノイドや口蓋扁桃肥大、口蓋垂(いわゆる、のどちんこ)周囲の軟口蓋が長い、舌が大きい、なども睡眠時無呼吸症候群の原因です。
顔つきの変化につながる、睡眠時無呼吸症候群の原因となる病気とは?
睡眠時無呼吸症候群による顔つきの変化を引き起こす合併症には、以下のようなものがあります。
- アデノイド・扁桃線の肥大
- 鼻づまりがある慢性副鼻腔炎(蓄膿症)
- 脳卒中
- 心機能低下
ここでは、どんな病気で、なぜ睡眠時無呼吸症候群が起きるのかを説明します。
アデノイド・扁桃線の肥大
アデノイドとは、鼻の奥の突き当たり、喉との間の上咽頭にあるリンパ組織のかたまりです。2歳頃から大きくなり始め、6歳頃に最大、10歳頃までには自然に小さくなります。扁桃肥大とは、口蓋扁桃が肥大する状態です。3歳頃から大きくなり始め、7歳頃に最大、やはり10歳頃には小さくなります。アデノイドや扁桃線が肥大していると、狭くて空気が通りにくいので、鼻づまりや口呼吸、いびきが起きるようになります。重症化した場合に起きるのが、睡眠時無呼吸症候群です。子どもでは、寝起きが悪い、強い眠気があり居眠りしてしまう、集中力が低下するなどが起こります。
子どもは風邪を引いた時に、鼻づまりや口呼吸、いびきを起こすことはあります。しかし、風邪が軽くなっても鼻づまりや口呼吸などが続く場合は、扁桃やアデノイド肥大を疑い、耳鼻咽喉科を受診しましょう。肥大があっても、呼吸障害や睡眠障害への影響が小さければ、経過観察します。
鼻づまりがある慢性副鼻腔炎(蓄膿症)
鼻の内部にある粘膜に覆われた空洞「副鼻腔」に風邪のウイルスや細菌が入り炎症が起きた状態のことを副鼻腔炎といいます。粘性で黄色の鼻水や頭痛、鼻水がのどに落ちる後鼻漏(こうびろう)などが主な症状です。急性副鼻腔炎が慢性化してしまい、3カ月以上続いている状態が慢性副鼻腔炎です。
慢性副鼻腔炎の人は、鼻がつまりやすい傾向にあります。鼻で呼吸ができずに、口呼吸するようになると、通常の鼻呼吸にくらべて、いびきをかきやすく、咽頭も狭くなりやすくなるので、睡眠時に無呼吸症状を起こすこともあるでしょう。
脳卒中
脳卒中とは、突然起きる脳血管の血流障害が原因で、手足がしびれて動かなくなったり、話せなくなったり、意識がなくなったりする発作のことです。
脳卒中を起こすと、高い割合で睡眠呼吸障害を併発するといわれています。これは脳卒中を発症したために、呼吸中枢が障害されたためだと考えられています。このように脳に障害があって発症した睡眠時無呼吸症候群が、中枢性睡眠時無呼吸症候群です。
心機能低下
脳の障害の他に、中枢性睡眠時無呼吸の原因になるものには、心機能低下があります。心臓の働きが低下し、全身に必要十分な血液を送り出せなくなった疾患が心不全です。心不全の約3割の方に中枢性睡眠時無呼吸があるといわれています。放置すると突然死する可能性もあります。
睡眠時無呼吸症候群の恐れのある人の顔つきの特徴

睡眠時無呼吸症候群の恐れのある人の顔つきの特徴には、以下のようなものがあります。
- 顔つき1. 顔の骨格に特徴がある
- 顔つき2. アデノイド・扁桃腺が大きい
- 顔つき3. 鼻づまりがある慢性副鼻腔炎(蓄膿症)により顔が腫れている
- 顔つき4. 脳卒中による顔の神経麻痺
- 顔つき5. 心機能低下による瞼のむくみ
自分や周りの人の顔つきと比較しながら、読みましょう。
顔つき1. 顔の骨格に特徴がある
睡眠時無呼吸症候群の恐れのある人は、顔の骨格に以下のような特徴があります。
- 顎が小さい
- 面長(顔が長い)
- 出っ歯などで、歯並びが悪い
欧米人に比べると、日本人は顔の形、あごの形、歯並びを原因として睡眠時無呼吸症候群を発症するケースが多くみられます。太っていなくても日本人は睡眠時無呼吸症候群を発症することが多いのです。扁桃が大きい人も、同様の理由で無呼吸を発症しやすくなります。
下顎が小さい人や面長(顔が長い)の人は、もともと気道が狭く、わずかな体重増加でも舌や首などに脂肪がつき気道が狭められるので、無呼吸を発症しやすくなります。日本人が太っていなくても睡眠時無呼吸症候群を発症することがあるのは、顔の形やあごの形、歯並びが原因である場合が多いようです。
顔つき2. アデノイド・扁桃腺が大きい
アデノイドや扁桃腺が大きい人の顔つきには以下のような特徴があります。
- 口元が前に出ている
- 二重顎になりやすい
- 顎と首の境目がわかりにくい
- 丸みを帯びた顔になる
顔つきの変化はアデノイドや扁桃腺の肥大によるものだけでなく、それによる口呼吸が原因で、成長するとともに特徴がはっきりしてきます。口呼吸していると、下顎の筋肉が未発達で、後退したしている顎や丸みを帯びた顔つきになります。
口呼吸の影響による変化は顔つきだけではありません。歯の咬み合わせにも影響して、叢生(デコボコ歯並び)や開咬(ポカン口)の原因にもなります。
顔つき3. 鼻づまりがある慢性副鼻腔炎(蓄膿症)により顔が腫れている
鼻づまりがある慢性副鼻腔炎(蓄膿症)の人は、場合により、顔が腫れているかもしれません。
副鼻腔は鼻のまわりの骨にある空洞で、前頭洞は2つ、左右のまゆのすぐ上に、上顎洞も2つ、左右の頬骨の中にあります。慢性副鼻腔炎(蓄膿症)で副鼻腔に膿がたまると、顔が腫れ、頬や目の奥などに痛みや圧迫感を感じる場合があります。
顔つき4. 脳卒中による顔の神経麻痺
脳卒中の人は、顔面神経麻痺になることがあります。「イーッ」と言ってもらって、口の片方だけしか動かないときは、顔の神経麻痺が起きている可能性が高いです。たいていは頭痛や意識障害、呂律が回らない、手足の麻痺やしびれなどの症状が併発します。一刻も治療が必要です。
顔つき5. 心機能低下による瞼のむくみ
心機能低下で、足や顔、特にまぶたがむくむことがあります。心機能が低下すると、心臓から十分な血液を送り出せません。腎臓に流れる血液も少なくなって、尿の量が減り、水分が体内に溜まるようになります。足の甲やすね、顔がむくむようになり、体重も増加してきます。
顔つきが上記特徴に当てはまったら睡眠時無呼吸症候群を疑おう

あなたの顔つきがこれまでの特徴に当てはまったら、睡眠時無呼吸症候群かもしれません。
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に起こるので、病気であることに気づかないこともあるでしょう。しかし、重症のまま治療をせず、放置していると命に関わる場合もあります。無呼吸・ 低酸素状態が続くので、心臓や血管に大きな負担がかかり、心筋梗塞や脳梗塞、高血圧、不整脈などが起こりやすくなるからです。放置せず、対処しましょう。ここでは、対処の仕方を2つ紹介します。
- 睡眠時無呼吸症候群の自分で出来る治し方
- 睡眠時無呼吸症候群で困ったら専門医に相談
あなたはどちらの方法で対処しますか。
睡眠時無呼吸症候群の自分で出来る治し方
睡眠時無呼吸症候群は、自分でも治せる場合があります。自分で出来る治し方にもいろいろありますが、主に以下のような方法があります。
- 肥満を改善:生活習慣を改善
- 仰向けで寝ない
- マウステープ:睡眠中の口呼吸をやめる
- あいうべ体操
太っている場合は、生活習慣を見直して、改善し、標準体重を維持しましょう。栄養バランスの取れた食事と適度な運動をして、規則正しい生活を送りましょう。
仰向けで寝ている方は横向きで寝てみることをおすすめします。横向きに寝ると、睡眠時無呼吸症候群が改善する場合があります。なぜなら、仰向けだと重力で舌の根本の舌根(ぜっこん)が気道に沈み易くなるからです。横向きの場合は仰向けの場合よりも沈みにくいので、喉は塞がりにくくなります。
睡眠中の口呼吸をやめて鼻呼吸するために、マウステープなどが役立つ場合もあります。「口閉じテープ」や「鼻呼吸テープ」などとして薬局や通信販売などで専用のものが販売されています。寝る前に縦に貼って休むだけです。すでに睡眠時無呼吸症候群で通院中の方は、事前に主治医に相談しましょう。
マウステープ(口閉じテープ・鼻呼吸テープ)の詳細については下記記事をご覧ください。
また、あいうべ体操とは舌と口周辺の筋肉のトレーニング方法です。口呼吸やいびきの改善に役立ちます。
あいうべ体操は以下のように行います。
- 「あー」と言いながら、口を大きく開ける
- 「いー」と言いながら、口を大きく横に広げる
- 「うー」と言いながら、口を前方に強く突き出す
- 「べー」と言いながら、舌を突き出し下に伸ばす
それぞれ1秒ずつを1セットとして、1日30セットを行いましょう。1回に30セットでも、10セットずつ3回に分けて行っても、好きな方法でしましょう。
下記記事でも舌のトレーニング方法をまとめています。併せてチェックしてみてください。
睡眠時無呼吸症候群で困ったら専門医に相談
睡眠時無呼吸症候群を疑っているときは、下記のいずれかの専門医を受診しましょう。
- いびき外来
- 耳鼻咽喉科
- 呼吸器内科
- 不眠や夜間の異常行動、日中の耐え難い眠気があるときは、精神科、脳神経内科
受診診療科はいびきや睡眠時無呼吸症候群を専門で治療しているいびき外来や耳鼻咽喉科、もしくは呼吸器内科です。いびきや無呼吸以外の症状、具体的には、不眠や夜間の異常行動、日中の眠気があるときは、精神科や脳神経内科の受診を検討するのがいいでしょう。
顔つきで睡眠時無呼吸症候群を疑ったらいびきメディカルクリニックにご相談ください

今回は、睡眠時無呼吸症候群の人は顔つきに特徴がある、睡眠時無呼吸症候群の恐れのある人の顔つきの特徴について、解説しました。
睡眠時無呼吸症候群の恐れのある人の顔つきには、特徴があります。特徴に当てはまったら睡眠時無呼吸症候群を疑いましょう。睡眠時無呼吸症候群は、重症のまま、放置していると命に関わることもありますので、放置せずに対処しましょう。
いびき・無呼吸治療をする専門医院いびきメディカルクリニックは今までに、多くの患者様を治療してきました。無料カウンセリングをしています。治療を受けてみたい方はぜひご相談ください。
<いびき・睡眠時無呼吸症候群の治療について詳しくはこちらからどうぞ>