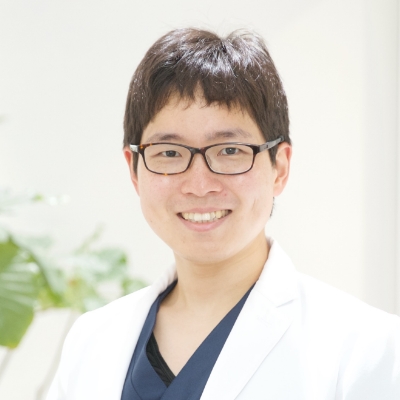睡眠時無呼吸症候群の原因は4つ!症状を判断・予防する方法

目次
睡眠時無呼吸症候群とは、その名称通り睡眠時に呼吸が止まってしまう病気のことです。
睡眠時という性質から、自分自身では病気の存在に気づきづらいのが特徴です。ほかにも、大きないびきをかくという特徴もあります。
このため、身近な人の睡眠を妨げる厄介な病気でもあるのです。
睡眠時無呼吸症候群は、いったい何が原因で発症するものなのでしょうか?
今回は、睡眠時無呼吸症候群の主な原因とともに、病気を判断する方法について解説いたします。
睡眠時無呼吸症候群の主な4つの原因

睡眠時無呼吸症候群には、全体の9割以上が発症する閉塞性睡眠時無呼吸症候群と、発症の確率が1割に満たない中枢性睡眠時無呼吸症候群の二種類があります。
特に閉塞性睡眠時無呼吸症候群を発症する原因は非常に多く、適切な判別が難しいのもこの病気の特徴の一つです。
その中でも、肥満・骨格・姿勢・呼吸中枢が原因であることが多いです。
ではなぜ、これらの原因が睡眠時無呼吸症候群を招いてしまうのでしょうか?
①肥満
肥満体型は、睡眠時無呼吸症候群の代表的な原因の1つです。
肥満体型の場合、喉や首の周りについた脂肪が仰向けで眠る際に重力によって気道を圧迫してしまうことで、呼吸が困難になり、いびきを発生させてしまいます。
そのいびきが無呼吸を呼び、無呼吸発作へとつながるため、最も多い症状と言われています。
また、肥満体型の場合は高確率で「閉塞型」の睡眠時無呼吸症候群です。
②骨格の問題
「閉塞型」の睡眠時無呼吸症候群の原因として、骨格の問題も指摘できます。
日本人には、下あごが小さい人が多く見られます。
下あごが小さい場合は仰向けで寝た際にあごが後退しやすく、気道を塞いでしまうケースがあるのです。
また、歯並びが悪い場合には、口腔内が狭くなり舌を収めにくくなります。
その結果、睡眠時には舌が気道にはみ出して塞ぐ形になってしまい、無呼吸の発生に繋がるのです。
関連記事:いびきの治療法を4つ紹介!原因に適した治療法を見つけよう
③睡眠中の姿勢
睡眠中の姿勢も、睡眠時無呼吸症候群の発症の可能性に関わってきます。
姿勢や体位次第では気道が狭くなってしまい、無呼吸のリスクが高くなるのです。
より具体的にいえば、横向きに寝るときよりも仰向けに寝るときのほうが無呼吸のリスク・発生頻度は高くなります。
加えて、無呼吸で息苦しくなった際に無理に呼吸をし続けると覚醒反応が起こります。
つまり、無呼吸が発生しているにも関わらず仰向けで寝続けた場合には、自ずと睡眠の質が低下してしまうのです。
日中の眠気の原因にもなるため、放置することはおすすめしません。
④中枢性の異常
呼吸中枢の異常により引き起こされる場合は、中枢性睡眠時無呼吸症候群と呼ばれます。
これは何らかの異常により、脳からの「呼吸しなさい」といった指令が通らなくなることで無呼吸に陥る病気です。
中枢性睡眠時無呼吸症候群が発症する原因は医学的に未解明であり、発症の確率も全体の数%のため極めて珍しい症状です。
ですが、心臓の疾患や、機能低下が見られる方を対象にした場合、3割から4割の確率で中枢性睡眠時無呼吸症候群を発症がみられるとされています。
睡眠時無呼吸症候群かどうか判断する方法

睡眠時無呼吸症候群は他者からの指摘で気がつくことが大半であり、自分自身で気がつくことが難しい病気です。
ですが、睡眠時無呼吸症候群の特徴的な症状を理解しておくことで、体の変化に気がつくことも可能になります。
他者からのいびきの注意が最も効果的でわかりやすい症状ですが、睡眠中の度重なる覚醒や起床時の口の渇きなども、無呼吸発作による症状です。
主な例を解説していきます。
周囲から指摘される
周囲から大きないびきや無呼吸を指摘されれば、睡眠時無呼吸症候群の可能性は高いといえます。
大きないびきをかくことも特徴の1つですので、家族や配偶者から「いびきがうるさい」などと指摘されるのであれば、病気を疑うべきかもしれません。
家族や配偶者に限らず、友人と旅行をした際に指摘されることで発覚するケースもあるようです。
日中の慢性的な眠気や倦怠感
睡眠時のいびきは無呼吸発作を呼び寄せ、脳を低酸素状態へと促します。無呼吸状態が一定以上続くと、睡眠時無呼吸症候群を発症するため、慢性的な眠気や倦怠感を抱いてしまうことになります。
ただの夜更かしや寝不足だろうと見逃してしまいがちな症状ですが、脳が低酸素状態になることで、日中の眠気や倦怠感、集中力の欠如の原因となり、不慮の事故を引き起こすケースが多いのもこの病の特徴です。
また、睡眠時無呼吸症候群を発症することによって、心筋梗塞や脳卒中などの合併症を呼び、命に関わる例も少なくありません。
日中のだるさや倦怠感は積み重なることでストレスとなり、精神疾患を患う危険性も考えられます。十分な睡眠時間を確保しているにもかかわらず眠気が取れないと感じている方は、睡眠時無呼吸症候群を疑う必要があるでしょう。
睡眠時無呼吸症候群の検査について

睡眠時無呼吸症候群の検査は、簡易検査(アプノモニター)と呼ばれるものと、脳波を含めた精密検査(ポリソムノグラフィー;PSG)の二段階の検査が必要になります。
簡易型アプノモニター
詳しい検査の必要があると診断された場合、この簡易型アプノモニターと呼ばれる検査を行います。
検査の内容は鼻や口の呼吸状態の確認、血中酸素濃度の測定です。
簡易検査は、自宅で貸し出しをして行うため、簡単な使い方の説明を受けるだけで行うことが可能です。
検査結果で睡眠時無呼吸症候群が診断された場合、精密検査(ポリソムノグラフィー)に移ります。
ポリソムノグラフィー
ポリソムノグラフィーとは、簡易型アプノモニターで睡眠時無呼吸症候群と診断された方が受ける精密検査のことです。
簡易型アプノモニターで調べた情報に加えて、脳波や心電図も追加で測定し、無呼吸の状態や体への悪影響をより精密に検査します。睡眠時無呼吸症候群の重症度を測るだけでなく、閉塞性によるものか、中枢性によるものかの診断も可能です。
ポリソムノグラフィー検査は、病院で一泊か二泊程度の入院が必要になります。
睡眠時無呼吸症候群を予防する方法

睡眠時無呼吸症候群を発症する原因は肥満や飲酒、生活習慣などが多いですが、人によっては処方されている睡眠薬が原因となっていることもあるため、原因に適した予防策が必要です。
主な原因の予防策と発症の関係性を説明していきます。
体重を減らす
睡眠時無呼吸症候群を発症する最も多い原因は、肥満体型であることです。
前述のように、肥満体型の場合は喉や首周りの脂肪による気道の閉塞により発症リスクが高くなります。
体重を減らすことで喉や首周りの脂肪を落とし、病気の原因となる気道の圧迫に対する予防に繋げることができます。
もちろん、そもそも肥満体型にならないように日々努めることも大切であるといえるでしょう。
過度なアルコール摂取を控える
アルコールには筋肉を弛緩させる効果があります。
そのため、過度な摂取をすれば、仰向けになった際に舌がより後退してしまい無呼吸に陥りやすくなるのです。
通常の状態でも就寝時には筋肉が緩むので、すでに症状が見られる人が過度のアルコールを摂取した場合には無呼吸に陥るリスクが高まります。
過度なアルコールの摂取は控えるようにしましょう。
睡眠薬の服用を医師に相談
睡眠薬の中には、無呼吸症状を悪化させるもの、または助長させるものが確認されております。
ただ単に寝付きが悪いという理由で診断を受けた場合に処方される睡眠薬は、寝つきを良くするためのものであり、筋弛緩作用が含まれています。
睡眠時無呼吸症候群の可能性がある場合、筋弛緩作用は気道の圧迫に繋がるため、医師にそのことを伝えた上で睡眠薬の処方をしていただかなければいけません。
また、中途覚醒は無呼吸発作が原因になっていることが多いため、無呼吸発作を改善するための治療を行ってみることで、睡眠薬が不要になることも十分にありえます。
口呼吸を防ぐための治療
睡眠時、口呼吸になる方はいびきや無呼吸発作を発症する確率が高く、睡眠時無呼吸症候群を呼び寄せてしまう傾向があります。
そのため、無呼吸発作の原因となる口呼吸の改善を試みることは、睡眠時無呼吸症候群の治療にも繋がります。
口呼吸の治療法はいくつかありますが、最も簡単で効果が見られるのは、唇をテープで止める口テープ睡眠という方法です。
それでも効果が見られない場合、いびきや口呼吸を改善するための専用のマスク、マウスピースなどが使われます。
枕の形状を見直す
枕を自身の体型に合ったものに変えることも、病気の予防や軽減のポイントです。
自分に合った枕であれば、寝姿勢でも気道が塞がりづらくなり発症を抑えることができます。
なお、枕選びで最も着目すべき点は高さであり、高すぎず低すぎないものを選ぶことが大切です。
仰向けの状態はもちろん、横向きになった状態でも違和感のない高さを選べば間違いはないでしょう。
睡眠時無呼吸症候群の主な4つの治療方法

睡眠時無呼吸症候群には、いくつかの治療方法があります。
症状ごとに適する治療方法は異なるので、内容をふまえた上で医師と相談しましょう。
CPAP療法
CPAP療法は睡眠中に専用のマスクを鼻に装着し、一定の圧力で空気を送るという治療方法です。
気道を通るように空気を機器から適度な圧力で送り込み、睡眠時の無呼吸を防ぎます。
機器はあくまでも患者の呼吸を補助する役割を担い、体には特別な変化をもたらさないため、継続的に使用する必要があります。
マウスピース
マウスピースによる治療は、あごが小さいことが原因で睡眠時無呼吸症候群を発症している人に有効です。
マウスピースを装着して下あごを前方に突き出すような形にすることで、舌の押し込み等による気道の閉塞を緩和させ、症状を和らげます。
手軽に利用できるといった利点がありますが、継続的な利用が必要であるほか、あごの痛みなどが生じる場合もあります。
外科手術
アデノイドや扁桃肥大から引き起こされる閉塞ならば、それらを摘出して治療する方法もあります。
肥大化した部分を切除することによって気道が広がり、症状の改善に期待ができます。
ただし、外科手術による治療は術後しばらく喉の痛みが続くとの声が多く、日常生活が辛いと感じる方もいるようです。また、術後2年〜3年後に無呼吸発作の再発が見られることもあり、無呼吸発作の素早い解決策としてのメリットは感じられますが、長期的な計画にはデメリットも感じられます。
パルスサーミア
パルスサーミアは、近年注目されている最新のレーザー治療法です。
イビキメディカルクリニックでも取り入れる治療法であり、従来の外科手術とは異なり、切除を伴わないため、様々なメリットがあります。
深部に影響を与えるレーザーにより、施術箇所の引き締めるため、ほかのレーザーに比べ表面の損傷が少なく済み、施術にはほとんど痛みを伴わずダウンタイムもほとんどありません。
定期的な施術を行う必要がありますが、効果の実感はより高いものとなるでしょう。
睡眠時無呼吸症候群は治療が必要!まずは原因を明確にしよう
主な原因には肥満や生活習慣が挙げられますが、中には骨格や顎の小ささなど、生まれ持った身体的特徴が影響する場合があります。
睡眠時に症状が発生するため、自分自身で気がつきにくい病気ですが、睡眠時無呼吸症候群について正しい知識と理解があれば、他者の指摘がなくとも気がつくことは可能です。
ただし、症状や原因によって治療法は異なり、場合によっては病気を助長させてしまう可能性もあり得ます。原因が不明な場合や、少しでも疑いを感じた場合はぜひ一度イビキメディカルクリニックへご相談ください。
【よくある質問】
Q. 睡眠時無呼吸症候群になる原因は何がある?
A. 無呼吸や無呼吸発作の症状は、主に肥満体型であること、過度な飲酒が見られることなど、生活習慣に関連する場合が多いです。また、睡眠薬に含まれる筋弛緩作用が影響していることもあります。
Q. 睡眠時無呼吸症候群はどのようにして気付くことが多い?
A. 睡眠時無呼吸症候群は自分自身で気がつきにくい病気のため、他者からいびきの指摘をされることで気がつくことが大半です。ですが、度重なる中途覚醒や、日中の眠気や倦怠感、起床時の口の渇きなど、自分自身で気がつける症状もあります。
新着記事
睡眠の質を上げたいあなたへ、新着記事をご紹介します。